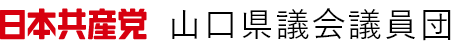2025年度予算編成に向けての諸課題について
1、防災対策の強化
◎藤本一規議員
質問の第1は、2025年度予算編成に向けての諸課題についてです。
第1は、防災対策の強化です。
能登半島地震などを受け、政府は、地方創生交付金を増額し、災害時に設置する避難所の環境改善に向けた取り組みを強化する方針を明らかにしました。遅きに失した感もありますが、一歩前進です。
急がれている1つは、避難所になる施設のトイレの洋式化と洋式・水洗タイプの災害用トイレの確保です。
県立学校体育館の洋式便器率は今年度当初で54.7%に留まっています。
大阪府は、今年度予算に、洋式・水洗タイプの組み立て式災害用トイレ500基と「トイレ・トレーラー」1台を購入する費用を計上しています。
2つは、避難所のエアコン設置です。
愛知県は今年度、福井県は新年度から、避難所となる県立学校体育館にエアコンを設置する予算を計上すると報じられています。
文科省が9月30日に公表した「公立学校施設における空調(冷房)設備の設置状況調査」によると、体育館等の設置率は県立高校は38.7%、特別支援学校は85.7%でした。この内、スポットクーラーを除くエアコンの設置率をお示しください。
山口県も新年度予算において、避難所となっている県立学校の体育館のトイレ洋式化と、エアコン整備を思い切って進めるべきです。また、災害用のトイレを確保すべきですが、お尋ねします。
●根ヶ山耕平副教育長
教育に関する数点のお尋ねのうち、まず、防災対策の強化についてお答えします。
最初に、県立高校の体育館等における、スポットクーラーを除く、エアコンの設置率についてですが、令和6年9月1日現在、県立高校が1.6%、特別支援学校が0.7%となっています。
次に、避難所となっている県立学校の体育館におけるトイレの洋式化についてですが、各学校の要望を踏まえながら、順次、整備をしています。
また、エアコンについては、建物の断熱性が必要であり、整備に多額の費用を要することから、スポットクーラー等、持ち運びが可能な空調機器の設置を基本に整備しているところです。
●佐藤茂宗総務部長
防災対策の強化のご質問のうち、災害用トイレの確保についてのお尋ねにお答えします。
県では、「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」を策定し、避難所の衛生環境を保つため、災害用トイレの十分な確保や、高齢者等に配慮した多目的トイレの確保を市町に対して求めているところです。
避難所の運営については、市町が地域の実情等を踏まえながら、主体的に行うものであり、災害用トイレの確保についても、各市町において適切に検討されるべきものと考えています。
なお、先般示されました国の総合経済対策において「避難所環境の抜本的改善」に取り組むこととされていることから、県としては、こうした国の動向も注視してまいります。
◎藤本一規議員【再質問】
日本トイレ研究会が行った地方公共団体における災害時のトイレ対策に関するアンケートに対して、山口県はトイレ対策の全体統括責任者を決めていないと回答しています。
この調査結果によると、全国44.6%の自治体が責任者を決めているということです。
今後避難所運営に係る各種指針の見直し作業を進めると本会議で答弁されています。
このトイレ対策の全体統括責任者を山口県決めるべきですが、お尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
県にですね、避難所関係の改善に向けて、トイレ対策の責任者を置くべきではないかどの再質問にお答えします。
トイレの確保を含む、避難者の生活環境の改善につきましては、避難所の運営主体である市町において適切に検討されるべきものと考えております。
◎藤本一規議員
3つは、落橋等防止性能がない橋りょうの対策です。
10月23日、会計検査院は、6事業主体が管理する354橋で、緊急輸送道路の橋で落橋等防止性能が確保されていないと、国交省に意見表示しました。資料1の通り県内では、48橋の落橋等防止性能が確保されていません。
国交省は、会計検査院の意見表示を受け、自治体などに「落橋等防止性能の対策が未了の橋りょうがある場合は、これを優先する」よう整備方針を示しました。県は、新年度からどのように対策を講じていこうとしているのかお尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
2025年度予算編成に向けての諸課題についてのお尋ねのうち、防災対策の強化に関する落橋等防止性能がない橋りょうの対策についてお答えします。
県では、緊急輸送道路上の橋梁や離島架橋などで耐震化を進めています。
このうち、緊急輸送道路上の橋梁において、「落橋等防止性能」の有無に加え、迂回路がないなど、路線の特性等も考慮した上で、耐震補強を実施する橋梁の優先順位を定め、「速やかな機能回復性能」の確保に取り組んでいるところです。
こうした中、先般、会計検査院から国に対し、「緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等について」の意見が表示されたことを受け、国から自治体などへ、「落橋等防止性能の対策が未了の橋梁がある場合は、当該橋梁を優先する」という整備方針が示されたところです。
県としては、国から示された整備方針も踏まえ、引き続き、県民の安心・安全の確保に向け、橋梁の耐震化を適切かつ計画的に進めてまいります。
2、中小企業の賃上げ等支援
◎藤本一規議員
第2は、中小企業の賃上げ等支援です。
1つは、県制度の拡充です。
県は、中小企業の賃上げのために22年度から制度融資を実施しています。これまでの実績をお示しください。23年度から奨励金を実施しています。昨年度と今年度の実績をお示しください。中小企業の賃上げはまさにこれからです。新年度も今年度と同様の制度融資と奨励金を実施すべきですがお尋ねします。
中小企業の最賃引き上げと生産性向上を一体で実施するのが、国の業務改善助成金です。11月12日時点で、国の助成金が支給された県内の事業者は、17件です。石川県は、業務改善助成金を受けた後の会社負担額の半分を負担する県の奨励金を実施しています。県は、国の業務改善助成金の会社負担を補助する制度を創設すべきですがお尋ねします。
●高林謙行産業労働部長
中小企業の賃上げ等支援についての御質問のうち、県制度の拡充に関する数点のお尋ねにお答えします。
①まず、令和4年度に創設した県制度融資「賃金引上げ・価格転嫁支援資金」の実績は、10月末で31件、4億9,300万円です。
②次に、昨年度実施した「賃上げ環境整備応援奨励金」の交付実績は、444件であり、今年度実施している「初任給等引上げ応援奨励金」は、11月末時点で454件の交付決定を行っています。
③次に、来年度の制度融資及び奨励金の実施については、現時点でお答えすることはできません。
④次に、国の業務改善助成金の事業者負担に係る県の補助制度の創設は考えていませんが、県では、本年度、奨励金の支給により若年層の賃金引上げを支援するとともに、デジタル化の段階に応じた補助制度等により、生産性向上を図っているところです。
◎藤本一規議員【再質問】
中小企業の賃上げですが、岩手県は新年度も中小企業の賃上げ支援を継続するともう表明しています。そして昨日、小池書記局長の国会質問でもあったんですが、徳島県は時給930円未満の従業員の賃金を980円以上に引き上げた中小企業等を対象に、一時金を支給する制度を創設したという風にあります。
山口県が中小企業賃上げ支援のために今年度の事業を継続するということは最低限の責務だと思いますけれども、是非、再度お尋ねします。
●高林謙行産業労働部長
中小企業の賃上げに係る県の事業について、来年度継続すべきとの再質問にお答えします。
先ほど御答弁申し上げたとおり、来年度の事業の実施の有無については、現時点でお答えすることはできません。
◎藤本一規議員
2つは、価格転嫁出来る仕組みの構築です。
県は、中小企業が価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのか。また、県が行う公契約で、価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのかお尋ねします。
●高林謙行産業労働部長
価格転嫁できる仕組みの構築に関するお尋ねのうち、中小企業が価格転嫁できる仕組みの構築についてお答えします。
県では、サプライチェーン全体での取引適正化により価格転嫁が着実に進むよう、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に、経済団体に対して、取引適正化に係る文書要請を行うとともに、「賃金引上げ・価格転嫁支援資金」による金融支援も行っています。
また、企業の賃上げに向けた環境整備にもつながる「パートナーシップ構築宣言」について、県のホームページや関係機関等を通じた普及啓発のほか、県補助金の加点措置も講じています。さらには、やまぐち産業振興財団に設置している「下請かけこみ寺」における取引に関する相談対応のほか、同財団と連携して、取引条件の改善に関する講習会を開催するなど、中小企業の円滑な価格転嫁が進むよう、環境整備に取り組んでいるところです。
●村岡嗣政知事
私からは、中小企業の賃上げ等支援に関して、公契約における価格転嫁できる仕組みの構築についてのお尋ねにお答えします。
地方公共団体が発注する公共工事等に係る公契約は、関係法令等に基づき、公平・公正な手続きによる適正な契約金額により締結されるものです。
本県においては、会計規則に基づき、昨今の物価上昇等、時勢を適切に反映した単価により算定された予定価格を基に契約を締結しています。
また、契約締結後においては、賃金や物価等の著しい変動が生じた場合は、単価改定やスライド条項の適用等により、適切に価格転嫁できる仕組みとなっております。
補助金行政の見直しについて
1、補助金行政の見直しについて
◎藤本一規議員
質問の第2は、補助金行政の見直しについてです。
第1は、山口ならではの特別な体験創出支援事業です。
1つは、周南市の事業者です。
補助金交付要綱に、補助対象経費に含まれないものとして「申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一生計者が経営する法人等との契約により相手方に支払う経費」とあります。本事業を運営する会社が地元に示した資料にある、事業実施主体と施設施工団体の登記簿を見ると、代表者と本社の場所が同じでした。県は、この事実をどうのように認識していますか。同一であるならば、申請者が経営する法人との契約であり、補助対象経費に含んではいけないという要綱の規定に該当しますが、県の認識をお尋ねします。
補助金交付要綱に、「補助事業の完了後においても観光連盟の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない」とあります。当初設置してあったトレーラーハウスのトレーラー部分は現在使用されていません。事業者は、トレーラー部分について、観光連盟に財産処分等承認申請書を提出したのかお尋ねします。
クルーズ船について、県は9月県議会で「明日から運航が開始される予定となっている」と回答しました。11月中旬に事業者に問い合わせると「クルーズ船の販売実績はない」と答えました。
補助金要綱に、「補助対象事業等に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合」は、「補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる」とあります。クルーズ船が今も稼働してないのなら、「怠慢」であり、事業者に補助金の一部の返還を求めるべきですが、お尋ねします。
2つは、山口市の事業者です。9月県議会で道免部長は「来年3月の完成に向けて予定どおり進捗している」と答えましたが、現時点の状況についてお尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
補助金行政の見直しについてのお尋ねのうち、山口ならではの特別な体験創出支援事業についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、補助対象経費に関する県の認識についてです。
施工業者については審査の段階で県も把握しており、観光連盟が金額や内容等も精査の上で交付要綱に基づく補助対象経費として認めていることから、要綱に反するものではないと認識しております。
次に、観光連盟への財産処分等承認申請書の提出についてです。
お示しのトレーラー部分は、補助目的である宿泊機能には直接関係のない部分であり、財産処分等承認申請書の提出は不要とされています。
なお、当初の補助目的のとおり、宿泊機能は確保されています。
次に、クルーズ船についてですが、事業者は10月から営業を開始しており、集客に向けた販売活動を積極的に行っていることから、補助金の返還を求めることは考えておりません。
次に、山口市の事業についてです。
現在、建築工事を行っており、来年3月の完成に向けて予定どおり進捗しているところです。
◎藤本一規議員【再質問】
体験創出事業についてです。部長、分けて答えてください。
周南市の事業者ですが、補助金申請者と、サウナ施工業者の経営者と本店の場所は登記上同一であるというふうに私は資料も示していますが、同一であるかどうか、はっきりその点分けて、いっぺんに答えずに、分けて、この点必ず答えてください。お尋ねします。
それで、同一であると私も現認しております。ならば、補助金交付要綱にある申請者が経営する法人と同一生計者が経営する法人等の契約により相手方に支払う経費は補助対象経費に含んでいけないと書かれてあることをどう観光連盟は業者に審査をしたのか県の認識を明確に答えてください。
それから、事業者が事業当初トレーラーハウスについて、建築基準法の許可を受けていなかったと思われます。トレーラーハウスであっても、電気、ガスなどを設置し、工具を使用しないと取り外すことのできない建物は、トレーラーハウスといっても建築基準法の適用を受けなければいけないというふうに思います。そうなりますと、今はいいんですけど、その前に建築基準法の許可を受けていなかったという不適切な対応が、行為が、事業者にあったのではないかということになれば、要綱上の補助金の一部返還を求める規定に該当しますが、観光連盟を指導すべきですがお尋ねします。
クルーズ船についてです。部長は明確に、10月1日から就航が開始されると答えたんです。事業者は未だに部長答弁が履行できていない。事業者の不明確な観光連盟に対する返答が、部長の答弁を生んだのなら、事業者は不適切な行為をしたということになり、これも、要綱上の補助金の一部返還を求めることに該当しますが、県はこの点観光連盟を指導すべきですがお尋ねします。
それから、補助金を交付しながら、事業をスタートした後にクルーズ船の停泊場所の確保の調整が遅れて、営業開始が遅れたという説明を私は受けていますが、これは観光連盟の審査に重大な問題があったと言わなければいけません。
クルーズ船も含めた提案で補助金を受ける以上、クルーズ船がサウナ施設の近くに停泊できるかどうか、観光連盟はちやんと審査したうえで、補助交付をすべきだったと思いますけども、補助金を出した後に、停泊場所が確保されていないから営業が開始できなかったというのは、これは問題にならないと思います。ここ重大な観光連盟の審査に問題があったと思いませんかお尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
補助金事業に関する数点の再質問にお答えします。
まず、申請者と施工業者が同一であると言うことを分けて答えて欲しいとのお尋ねです。
お示しの施工業者が同一であるということについては、これまで申し上げておりますが、審査の段階で把握をしております。
次に、その場合に補助対象経費に含まれないとしているが、その点をどのように審査したのかとのお尋ねです。
交付要綱の別表に、補助対象経費の「その他」として「事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費」を補助対象経費とする旨が規定されております。
当該経費については、観光連盟が事業者から聴き取りを行い、工事の特殊性の確認や見積の精査等を行った上で、この規定に基づき補助対象とされたものです。
次に、当初設置していたトレーラーハウスは建築基準法の適用になるのではないか、許可を受けていなかったのは不適切であり、観光連盟を指導すべきではないかとのお尋ねです。
当初設置したトレーラーハウスについては、給排水等の設備など、簡易に着脱が可能であって、建築基準法の適用を受けないということを事前に確認をしております。
したがって、観光連盟を指導するということは考えておりません。
次に、クルーズ船について、「10月から運航が開始される」という答弁であったけれども、結果的に、事業がなされていないというのは、事業者の報告が不明確であったのではないか。
補助金の返還の事由にあたるのではないかというお尋ねです。
前回答弁において「10月から運航が開始」と申し上げたのは、営業が開始されるということを意味したものであって、実際に営業が開始されておりますことから、事業者が不明確な報告を行ったというものではありません。
したがって、補助金の返還を求めるということは考えておりません。
次に、クルーズ船の停泊場所が確保されていることを確認してから補助金を出すべきであって、審査に暇疵があったのではないかとのお尋ねです。
クルーズ船の停泊場所の確保が遅れたということについては、本補助金の採択後に生じたものであって、審査に不備はございません。
◎藤本一規議員【再質問】
それからトレーラーハウスについて、私に情報が入ったところでは、現認もしていますが、平生町のケースで、今年の秋以降に建築基準法の適用を受けたと、で、許可が出されたということですが、いつ許可が出たのか土木部長お答えください。
●大江真弘土木建築部長
まず、山口ならではの体験創出補助金の補助を受けた事業者が平生町内で建てたトレーラーハウス。建築確認の許可はいつなされたかとのご質問かと思います。ご質問に許可とございますが、法令上、確認となっておりますので、その点でお答えいたします。
お尋ねのトレーラーハウスに係る建築確認は、民間確認検査機関である「一般財団法人山口県建築住宅センター」へ申請がなされまして、令和6年9月12日付けで確認済証が交付されております。
◎藤本一規議員【再々質問】
体験創出補助金です。私としては、初めてこの補助金申請業者とサウナ施工業者が同一だということをお認めになる発言を本会議場でしていただきました。
その点で、特殊性とか言われましたけれども、その観光連盟の審査の内容は、私たちわからないわけです。やっぱりそのもう一つのその規定である、例えば、同じ業者が中抜きとかをしてはいけないということで、申請者と同一生計者が経営する法人との契約を規定する要綱があると思うんです。
やっぱり、そこで補助経費としてはいけないということを観光連盟が補助経費としたっていうことは、改めて、説明を受けた上で重大問題と言わなければなりません。
そして、トレーラーハウスについて、9月前にですね、建築基準法の許可を受けなくてもよかったというのは、私は見てないから分からないし、工具や電気などをとらなければトレーラーとして使えないというような施設であったのかどうか、わからないんですから、観光連盟の審査はやっぱり現時点、不十分だと言わなければならないと思います。
それから、一番わかりやすいのは、未だにクルーズ船が就航できていないということです。まあ、停泊場所を確認して、クルーズ船に対する補助を出すのが、当たり前だと思います。この点は、重大な観光連盟の審査に問題があったと思います。
私は、総じて、本事業に対する観光連盟の審査に重大な問題があったことを指摘をして、山口県補助金等交付規則9条、観光連盟に対してやっぱり報告を、県は求めるべきだと思います。お尋ねします。
それで、これだけ疑義のある体験創出補助金、新年度予算化すべきでないと思いますけれども、お尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
補助金事業に関する再々質問にお答えをします。先ほどお答えした3点について特に問題点がある。これについては、観光連盟の審査に問題があったのではないか、そうであれば、県の補助金規則9条に基づいて、観光連盟から報告を受けるべきではないかとのお尋ねだったと思います。
先ほどもお答えしたとおり、ご指摘の点については、いずれも観光連盟において、適切な対応がなされており、審査に問題があったとは考えておらず、したがいまして、報告を求めることは考えておりません。
次に、このような補助金制度を新年度予算化すべきではないのではないかとのお尋ねですけれども、来年度以降の取り組みについて現時点でお答えすることはできません。
2、柳井地域広域水道企業団への補助金
◎藤本一規議員
第2は、柳井地域広域水道企業団への補助金です。
資料2は、県内市町の水道料金を示したものです。柳井地域広域水道企業団から受水している柳井市、田布施町、平生町、周防大島町、上関町の水道料金は4~5千円台である一方、その他の14市町の平均は2657円です。
柳井広域水道の弥栄ダムにある水利権は日量5万トンです。3万トンが事業化分で、2万トンは、未事業化分となっています。
県は、未事業化分の2万トンの企業債等の元利償還金相当額を「水道広域化促進事業」補助金として、企業団及び関係市町に支出しています。
また、「水道料金安定化対策事業」補助金として、柳井地域と同様にダムから直接原水を受水している市町の平均水道料金の1.5倍を超える相当額の2分の1を関係市町に支出しています。補助基準1.5倍を引き下げ、柳井地域の水道料金を引き下げるべきですが、お尋ねします。
弥栄ダムから柳井市日積までの導水施設は、小瀬川第二期工水と柳井広域水道は共用しており、維持管理経費は、水道が5万トン、工水が6千20トンで按分されています。水道は、2万トンの未事業化分が含まれる一方、工水は、3万2千トンの未事業化分が含まれていません。導水施設の按分を水道の未事業化分の2万トンは除いたものにすべきですがお尋ねします。
今年度、企業団が国に払うダム分担金等は、5万トン分の8456万円です。事業化分の3万トンなら、6149万円となり、未事業化分2万トン分2300万円を余分に払っており、この部分が、水道料金を高止まりさせる一因です。
県は、小瀬川第2期工水の未事業化分3万2千トンについて、水資源対策推進協議会で活用方策を検討しています。県は、柳井広域水道の未事業化分2万トンについても、工水の未事業化分と合わせ、国への治水振り替えを含め、活用方策を検討すべきと考えますがお尋ねします。
●近藤和彦環境生活部長
補助金行政の見直しについての御質問のうち、柳井地域広域水道企業団に関する2点のお尋ねにお答えします。
まず、「水道料金安定化対策事業」補助金の補助基準の引き下げについてです。
当該補助金は、弥栄ダムからの遠距離導水等により高料金となっている1市4町の水道料金の上昇抑制を通じて、県内の料金格差の拡大を抑えることを目的としているものであり、引き続き、こうした考えのもと、必要な支援を行ってまいります。
次に、柳井地域広域水道企業団の未事業化分2万トンの活用方策についてです。
未事業化分2万トンは、企業団が権利を保有していることから、その活用方策については、必要に応じて、企業団において検討されるものと考えています。
●米原圭太郎企業局長
柳井地域広域水道企業団への補助金に関するご質問のうち、導水施設の維持管理経費の按分についてのお尋ねにお答えします。
弥栄ダムから柳井市日積までの導水施設については、上水を日量5万トン、工業用水を日量6千20トン導水するために建設したものであることから、導水施設の維持管理経費については、それぞれの導水能力により按分すべきと考えています。
◎藤本一規議員【再質問】
柳井広域水道の問題についてだが、県は、ダム開発事業費と導水施設の建設費の未事業化分2万トンの企業債等元利償還金相当額を補助していると、先ほど言った。
しかし、導水施設の維持管理経費については、地元に未事業化2万トン分の負担を求めており、これに差があってはいけない。
導水施設の維持管理経費の未事業化分についても、地元負担はとらないよう、県の新たな対応を求めたいと思うが、伺う。
高料金対策補助金について、宇部、山陽小野田や下関だが、直接ダムから受水する料金の平均の1.5倍とされているが、平均ではなく、なぜ1.5倍にしたのか、根拠を示せ。
補助基準額は、平均にすべきだと思うが、尋ねる。
●近藤和彦環境生活部長
まず、柳井地域広域水道企業団への補助金についてのお尋ねがありました。
最初に、導水管の維持管理経費のうち未事業化分の2万トンについて、県が、補助するべきではないかというお尋ねです。
県では、国による水道の高料金対策が、資本費負担の軽減に対して措置されていることに準じて、導水管等の建設費の補助を行っているところであり、維持管理経費まで補助することは、考えていません。
高料金対策における補助基準の1.5倍について、なぜ1.5倍なのか、柳井地域と同じくダムから直接導水している3市の平均値にすべきではないか、とのお尋ねです。
当該高料金対策の補助基準については、「水道料金は、全国平均の1.5倍以内であることが望ましい」とする国の生活環境審議会の答申に準じて定めており、現時点では、変更することを考えていません。
◎藤本一規議員【再々質問】
柳井広域水道について、一般会計に移管した小瀬川第2期工業用水道の未事業化分3万2千トン、これはダム分担金が4千万円、県民の税金から使われていることは過去の議会でも指摘した。
そして、柳井広域水道の未事業化分は、ダム分担金が2万トン分で約2千3百万円支出している。
これは利益を生まない水に、県民の税金、柳井では水道の受益者負担増となって表れている。
工水も水道も、この未事業化分の水利権を国に返還するための国との交渉に、本格的に腰を入れるべきである。
県と柳井地域の自治体が一緒になって、未事業化分の水利権を国に返還するための交渉を行うべきだと思うが、尋ねる。
●近藤和彦環境生活部長
柳井地域広域水道企業団の未事業化分2万トン分についての国への協議という再々質問の御趣旨だったと思います。
先ほど御答弁を申し上げておりますけれども、この未事業化分2万トンは、まずは、必要に応じて、企業団において検討されるものと考えておりまして、その検討状況を待って判断をしていきたいと考えております。
環境問題について
1、 PFAS問題
◎藤本一規議員
質問の第3は、環境問題についてです。
第1は、PFAS問題です。
1つは、米軍岩国基地でのPFAS調査です。
米軍岩国基地周辺のPFASをめぐり、岩国市は10月22日、国や県にモニタリング調査を依頼したと報じられました。
9月県議会で、平屋副知事は「岩国市の依頼内容を確認し、国とも連携しながら、調査の必要性について検討」すると答えました。岩国市からどのような依頼があったのか、県は、国と調査の必要性についてどのような検討を行っているのかお尋ねします。
●近藤和彦環境生活部長
次に、環境問題についての数点の御質問のうち、まず、PFAS問題についての2点のお尋ねにお答えします。
岩国市からは、県において、過去に調査を行った環境基準点を含め、公共用水域における水質調査で、P FASのモニタリングを継続的に実施するよう要望がありました。
県では、同様に岩国市から要望を受けた環境省と11月から協議を始めており、来年度に向けて、岩国基地周辺の環境基準点等での調査の必要性を検討しているところです。
◎藤本一規議員【再質問】
岩国市からモニタリング調査の依頼があったと、そして、11月から国と協議している。そして来年度以降、調査をするというようなことですけれども、もう少しですね、国との調整はどのような内容で調整しているのか。いよいよ調査を開始する時期はどうなのか、お尋ねしたいと思います。
●近藤和彦環境生活部長
PFAS問題について1点お尋ねがあったと思います。
県では、環境省とどのような調整をしているのか、来年度どんな調査をするのか、というところですけれども、県では環境省に、P FAS調査に対する考え方、調査の内容とか、あるいはその今後、調査のいろんな基準の見直しが検討されておりますので、そういった対応に関する考え方を収集しながら、後は県において来年度に向けて、岩国基地周辺で測定地点、環境基準点とするのかどうか、あるいは測定回数をどうするのかどうか、そういった調査の必要性を検討しているところです。
◎藤本一規議員
環境省は8月に、PFASに対する総合戦略検討専門家会議(第5回)を開きました。この際の会議資料に基づきお尋ねします。
まず、PFОS等含有泡消火薬剤の在庫量調査です。①県内の消防機関、②山口宇部空港、③県内の自衛隊施設、④米軍岩国基地、以上、4施設の在庫量をお示しください。
2つは、水道におけるPFОS及びPFОAの全国調査についてです。
5月29日付で、国土交通省と環境省は、全国の水道事業者などに対し、水道におけるPFОS及びPFОAに関する調査を実施し、11月29日付で結果が公表されています。県内での結果をお尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
次に、PFAS問題の御質問のうち、県内の消防機関及び自衛隊施設のPFOS等含有泡消火薬剤の在庫量についてお答えします。
環境省が11月1日に発表した調査結果によると、消防機関では5,700リットル、自衛隊関連施設では1, 920リットルの在庫があるとされています。
◎藤本一規議員【再質問】
岩国基地のPFAS調査についてです。だいぶ具体的な答弁が出てまいりました。岩国市からモニタリング調査の依頼があったと、そして11月から国に、国と協議をしていると、
そして来年度以降調査をするというようなことですけども、もう少しですね、国との調整はどのような内容で調整しているのか、いよいよ調査を開始する時期はどうなのか、お尋ねしたいと思います。
それから、環境省の11月1日のPFAS含有泡消化薬剤の在庫量の結果ですけれども、私も環境省の資料で現認をしています。P FOSが宇部空港に3, 700リットル、そしてPFOAが消防機関に5, 700、自衛隊関連施設に1,920.さて、これら、宇部空港はわかりますけれども、消防機関とはどこか、自衛隊施設とはどこなのか。
そして、総じて、空港、消防機関、自衛隊関連施設、廃棄の見通しは立ってるのか。さっき、米軍基地はもう廃棄できたと明言されましたので、あるうちはまだ問題があるわけですね。廃棄までいつたどり着くのか、認識をお尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
次に、PFAS問題の関係で、消防機関と自衛隊施設、どこにその在庫があって、これからどういう形で処分がされていくのかの見通しでございます。
まず、消防機関でございますが、県が消防を通じて調べたところによりますと、宇部・山陽小野田消防局に5, 600リットル、美祢市消防本部に100リットルの在庫がござい
ます。いずれもP FOSではなくP FOAでございます。
そちらのP FOAの在庫がある消防機関におきましてはP FOAを含まない代替の泡消火薬剤との交換を進めていく予定と聞いておりまして、いつまでかという時期については現在確認が取れていない状況でございます。
次に、自衛隊の関連施設でございますが、内訳につきましては承知をしていないところでございます。
なお、環境省の資料によりますと、1,920リットルの在庫は全てPFOAであるということでございます。
防衛省・自衛隊におきましては、今後、P FOAを含まない泡消火薬剤の代替の促進を図っていくとのことでございまして、防衛省・自衛隊におきまして適切に対応されていくものと考えております。
◎藤本一規議員
環境省は、8月に、PFASに対する総合戦略検討専門家会議(第5回)を開きました。この際の会議資料に基づきお尋ねします。
まず、PFОS等含有泡消火薬剤の在庫量調査です。①県内の消防機関、②山口宇部空港、③県内の自衛隊施設、④米軍岩国基地、以上、4施設の在庫量をお示しください。
●大江真弘土木建築部長
次に、PFAS問題についてのお尋ねのうち、山口宇部空港のPFOS等含有泡消火薬剤の在庫量についてお答えします。
山口宇部空港では、PFOS等を含まない泡消火薬剤への交換を既に完了しており、現在、処分予定の3, 700リットルのPFOS含有泡消火薬剤を保管しています。
●田中康史総務部理事
米軍岩国基地のPFOS等含有泡消火薬斉Iの在庫量についてお答えします。
国からは、「米軍岩国基地については、令和4年12月までにPFOS等を含まない泡消火薬剤への交換を完了し、また、PFOS等を含む泡消火薬剤は、日本国内の認可された処分施設で廃棄処理を完了した」との説明を受けています。
◎藤本一規議員
それから環境省の11月1日のP FAS含有泡消化薬剤の在庫量の結果ですけれども、私も環境省の資料で現認をしています。P FOSが、宇部空港に3,700リットル、そして、PFOAが、消防機関に5, 700、自衛隊関連施設に1,920。
さて、これら、宇部空港は分かりますけれども、消防機関とはどこか、自衛隊施設とはどこなのか。
そして、総じて空港、消防機関、自衛隊関連施設、廃棄の見通しは立っているのか。さっき米軍基地はもう廃棄できた明言されましたので。あるうちはまだ問題があるわけですね。廃棄までいつたどり着くのか認識をお尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
山口宇部空港の関係でいつまでに処分するのか、廃棄までいつたどり着くのかとのお尋ねでございます。
保管しておりますP FOS含有泡消火薬剤については、現在、処分の準備を進めているところであり、できるだけ速やかに処分することとしております。
◎藤本一規議員
2つは、水道におけるPFОS及びPFОAの全国調査についてです。
5月29日付で、国土交通省と環境省は、全国の水道事業者などに対し、水道におけるPFОS及びPFОAに関する調査を実施し、11月29日付で結果が公表されています。県内での結果をお尋ねします。
●近藤和彦環境生活部長
次に、全国の水道におけるPFOS及びP FOAに関する調査結果についてです。
当該調査は、令和2年度から本年9月までに水道事業者等が実施したP FOS及びP FOAの水質検査結果をとりまとめ、公表されたものです。
これによると、県内の検査結果は、全て、国が定めた暫定目標値内でした。
なお、1市3町の6事業は、検査未実施となっています。
2、阿武風力発電について
◎藤本一規議員
第2は、阿武風力発電です。
「阿武・萩の未来を良くする会」など3団体は、11月20日、武藤経産大臣らに、HSE株式会社が阿武町に計画している風力発電事業の失効を求める要望書を提出しました。私は、辰巳衆議院議員とともに同席しました。
HSEは、今年3月9日の提出期限までに新規確認申請を行うことが出来ませんでした。HSEは、経産省に、必要書類を提出できなかった理由について①環境アセスメントが進んでおらず権原が確定できない、②23年に隣接地が保安林に指定されたため、その解除が必要となり、想定外の手続きが必要となった、などと説明し、経産省は「事業者の責によらない事情であることから状況を注視しつつ26年3月30日まで提出を待つ」と判断しました。
要望書は、①について、権原の確定の可否は環境アセスメントを進めていないHSEの責によるもの、②について、23年に保安林に指定された土地は、対象事業実施区域に隣接しておらず、HSEは保安林の解除の申請を行っていない、などを指摘し、事業者が経産省に行った説明は事実と異なっており、事業を失効させるよう求めています。
辰巳衆院議員は「HSEの説明に疑義が出されている点については、事業者に再度、聞き取りを行うべきだ」と質し、資源エネルギー庁の担当者は「疑義が出されている点については、当時の資料を精査する、必要な場合事業者へのヒアリングを行う」と答えました。県は、国に、HSEに対する丁寧な再調査が行われるよう求めるべきですがお尋ねします。
●鈴森和則産業労働部理事
阿武風力発電に関する御質問のうち、事業者に対する国の再調査についてのお尋ねにお答えします。
再生可能エネルギー発電事業については、電気事業法や再エネ特措法に基づき、国が監督権限を有しています。
従って、再エネ特措法に基づく個別具体の事業計画の認定や個々の認定事業者の報告徴収をどうするかは、国の責任において判断されるべきものであり、国に対し、お示しのような再調査に関する対応を求めることは考えていません。
◎藤本一規議員
次に環境アセスメントです。
HSEが保安林の解除について言及している場所は、現在の対象事業実施区域から300㍍以上離れていることが予想されます。HSEが今後のアセスメント手続きで、修正前の区域から300㍍以上離れた区域を新たな区域とする場合、方法書から手続を経るよう指導すべきですがお尋ねします。
山口県・島根県両県をまたぐ(仮称)西中国ウインドファーム事業の配慮書に対する島根県知事意見は、「事業の廃止」としたのに対し、山口県知事意見は「事業計画の見直し」としか言及していません。
私が、この点などを指摘したことに対し、環境省の担当者は、環境大臣意見や知事意見で、事業の「中止」や「廃止」という表現が使われていると回答しました。県は、今後の阿武風力発電事業に係る知事意見において、「中止」や「廃止」に言及すべきと考えますが、見解をお尋ねします。
●近藤和彦環境生活部長
次に、阿武風力発電についての御質問のうち、環境アセスメントについての2点のお尋ねにお答えします。
まず、方法書から手続を経るよう県が事業者を指導すべき、とのお尋ねです。
環境影響評価法において、県の役割は、手続の各段階で適正に意見を述べること等とされており、県には、事業者を指導する法的権限はありません。
次に、今後の知事意見において、事業の「中止」や「廃止」に言及すべき、とのお尋ねです。
環境アセスメントは、事業の可否を問うものとは位置付けられていないとの認識の下、本県では、これまでも事業の「中止」や「廃止」などの表現を用いていないところであり、今後も、環環保全の見地から適切な知事意見を述べてまいります。
教育問題について
1、山口県立大学と自衛隊について
◎藤本一規議員
質問の第4は、教育問題についてです。
第1は、山口県立大学と自衛隊についてです。
2020年度以降、県立大学と陸上自衛隊山口駐屯地第17普通科連隊が、「共同研究」を行っています。具体的には、自衛隊山口駐屯地の自衛官募集のための広報映像作成における撮影・編集に関する技術協力等についての「共同研究」です。
山口県立大学定款に大学の目的は「住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する」こととあります。人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチは、「国際法上、教育の軍事利用は、教育機関を合法的な軍事目標に変える可能性がある」「学校と大学の利用の可能性、教育の質、学ぶ機会を低下させることは、国際人道法上で定められている教育を受ける権利の侵害に繋がる可能性がある」と述べています。自衛隊との共同研究は、大学の目的からも問題があると考えますが、お尋ねします。
また、同大学が撮影機材を自衛隊に貸し出し、自衛隊は撮影した動画を同大学に提供し、昨年度から山口駐屯地記念行事の中で、共同のブースを設置し、VR動画を子どもたちに見せていたことも判明しました。今年の動画の一つが、戦車乗車体験でした。
市民団体によると県教委は1985年に市民団体の要請に対し、「自衛隊駐屯地の公開への児童生徒の参加に当たっては、危険防止の立場から武器に触れることや戦争賛美となることなど自他の生命や人格を尊重する精神を損なうことがあってはならない」と答えたとされています。
疑似的であっても武器に触れさせる教材を県立大学が自衛隊と共同で作成し、子どもたちに提供することは先の県教委の見解から問題があると考えますが、お尋ねします。
●佐藤茂宗総務部長
次に、教育問題に関するお尋ねのうち、山口県立大学と自衛隊についての2点のお尋ねにまとめてお答えします。
県立大学は、研究成果の社会への還元による地域貢献活動を展開することも目的としており、地域の課題解決を図るため、様々な分野で、企業や自治体等との共同研究を積極的に実施しています。
県立大学からは、お示しの共同研究は、こうした目的に沿ったものであり、また、作成したVR動画の提供についても、子どもたちに与える影響に配盧していることから、問題はないと考えていると聞いています。
県としては、県立大学において適切に対応されたものと考えています。
2、総合支援学校の寄宿舎について
◎藤本一規議員
第2は、総合支援学校の寄宿舎です。
文科省は、2012年「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」で、寄宿舎について「入居した障害のある児童生徒等が毎日の生活を営みながら、生活のリズムをつくるなど生活基盤を整え、自立し社会参加する力を養う貴重な場である」としています。学校教育法第78条に「特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない」とあり、寄宿舎は、全ての特別支援学校に合理的配慮の基礎となる基礎的環境整備として位置づけられるものです。
資料3の通り、県内の総合支援学校4校にある寄宿舎7棟は、築44年以上経過しており、至急、建て替え計画を立案すべきですが、お尋ねします。
●根ケ山耕平副教育長
次に、総合支援学校の寄宿舎についてですが、学校からの要望を踏まえ、必要に応じて、修繕や改修を行っているところであり、建て替え計画の策定までは考えていません。
◎藤本一規議員【再質問】
宇部総合支援学校の寄宿舎を見学した。居室の入口に段差があり、肢体不自由と重複した障害を持った児童生徒が利用できない。
県教委は、法律を受けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領やリーフレットを作成している。
総合支援学校が含まれるのは当然であり、44年以上経っている訳だから、大規模改修ではなく、寄宿舎の建て替え計画の立案が避けて通れないが、尋ねる。
●根ケ山耕平副教育長
配慮が必要な児童生徒が入舎する際は、段差解消のためのスロープや手すりの設置など、合理的配慮の観点から、必要なバリアフリー改修を行うこととしております。
また、繰り返しになりますが、建て替えにつきましては、学校からの要望を踏まえ、必要な修繕や改修を行いながら使用することとしており、建て替えまでは考えていません。
3、いじめ問題について
◎藤本一規議員
第3は、いじめ問題です。
1つは、重大事態への対応です。
令和5年度の千人当たりの重大事態発生件数は全国平均が0.10に対し、山口県は、0.17です。今年2月、文科省は山口県など千人当たりの重大事態発生件数が多い自治体に、「いじめ重大事態に関する個別サポートチーム」を派遣しました。山口県は、どのような指導助言を受けたのかお尋ねします。
文科省は、8月「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を改定しました。県は、ガイドラインの改訂を今後の重大事態の調査に生かすのかお尋ねします。
2つは、新南陽高校での重大事態への対応です。
今議会に、新南陽高校で発生した重大事態に関する調査と処分の請願書が提出されました。請願書は、早急な、第三者調査委員会の設置などを求めています。
学校が本件を「重大事態」と認定したのは、昨年1月です。1年10カ月経過した現在まで、第三者調査委員会が設置されていない状況は看過できません。その理由と今後の見通しをお示しください。
●根ケ山耕平副教育長
次に、いじめ問題に関する数点のお尋ねについてです。
まず、本県に派遣された「いじめ重大事態に関する個別サポートチーム」からは、文部科学省がとりまとめた、「いじめ対策に係る事例集」を参考にすることなどにより、いじめ対策の一層の充実を図るよう指導助言があったところです。
次に、8月に改訂された国のガイドラインでは、調査組織の中立性・公平性を確保する必要性の高いケースなどが具体的に示されており、県教委では、このガイドラインに沿って、いじめの重大事態に適切に対応しています。
次に、お示しのありました県立高校での重大事態への対応については、個別の事案であることから、お答えを差し控えさせていただきますが、国のガイドラインに沿って、適切に対応しているところです。
宇部市に係る問題について
1、長生炭鉱水没事故について
◎藤本一規議員
質問の第5は、宇部市に係る問題についてです。
第1は、長生炭鉱水没事故です。
長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会と市民の共同によって長生炭鉱の坑口が開き、10月26日、日韓両国からの遺族が参加し、追悼式が行われました。10月30日には、坑口から初めての潜水調査が行われました。ダイバーの伊佐治さんは、約180㍍先まで潜水し「継続してやれば遺骨は回収できるはず」と述べました。
9月県議会で、県は「宇部市と情報を共有しながら、適切な形で要望等を国に伝えてまいります」と答えました。資料4は、2018年以降の国への要望伝達状況を示したものです。至急、国を訪問し、遺骨収集を要望すべきですがお尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
次に、宇部市に係る問題についてのお尋ねのうち、長生炭鉱水没事故についてお答えします。
お示しの長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、犠牲者の方々に哀悼の意を表します。
現時点、国を訪問し、遺骨収集について要望する予定はありませんが、県としては、国の動向も確認しながら、引き続き、日韓親善と人道上の立場から、「刻む会」の皆様などからの御要望等を適切に国に伝えてまいります。
◎藤本一規議員【再質問】
昨日、共産党の小池晃議員が長生炭鉱の問題を国会の参議院の代表質問で取り上げました。国として発掘調査すべき、と。
石破首相が答えました。「長生炭鉱の遺骨は、現時点で、場所が特定されていない」という、従来の答弁がありましたけれども、後半部分は、「国内に存在する旧朝鮮半島出身労働者の遺骨についても、遺族が希望する場合は、可能な限り返還することが望ましい」と。
だから、長生炭鉱の遺骨が発見されたら、石破首相の答弁では返すべきだと。今は、わからないというものですけれども。
刻む会は来年1月に再度、坑口からの潜水調査を行う計画です。
県として、年度内に、国に直接出向いて要望するという答弁だったのでしょうか、お尋ねします。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
現時点で、国に直接出向いて要望する予定はありませんが、県としては、日韓親善と人道上の立場から、引き続き「刻む会」の皆様などからの御要望を適切に国に伝えてまいります。
2、県立宇部西高校の跡地利用について
◎藤本一規議員
第2は、県立宇部西高の跡地利用です。
我が子も学んだ宇部西高校が来年度で幕を閉じようとしています。1万7500人を超える県民が宇部西高校の存続を求めたことを改めて指摘します。
宇部西高は造園や園芸のコースがあり、県道から校地に入った瞬間から、学校全体が植物園の様です。跡地は、県又は宇部市が所有し、県民が集う目的で利活用されるべきと考えますがお尋ねします。
●根ケ山耕平副教育長
次に、県立宇部西高校の跡地利用についてですが、在校する生徒が安心して学習に取り組めるよう配慮する必要があることから、現時点、検討していません。
(2024年12月5日)