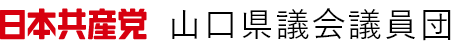◎河合喜代議員
先の総選挙で、自民、公明両党は「与党過半数割れ」に追い込まれるという歴史的大敗を喫しました。長く続いた自民党政治への厳しい国民の審判が下ったことは明瞭です。大局的に見れば、国民が自民党政治に代わる新しい政治を模索し、探求する、新しい政治プロセスが始まったことを示すものです。日本共産党は、この歴史的結果を心から歓迎するものです。
この政治の激動をつくりだすうえで、決定的な役割を果たしたのは、自民党の政治資金パーティーによる裏金づくりを暴露し、さらに選挙の最中に、裏金非公認議員にたいする政党助成金からの2000万円の支給をスクープした「しんぶん赤旗」と日本共産党の論戦でした。選挙戦の終盤で、与野党ともに「空気が激変した」というほど、日本共産党は、自公政権を追い詰めるうえで大きな貢献をすることができたと自負しています。
この間、安倍、菅、岸田政権が推し進めたアメリカいいなり、大企業優遇の政治を礼賛してきた山口県政への審判でもあるのではないかと考えます。そうした立場から通告に従い質問をいたします。
2025年度予算編成方針について
1、「課税最低限」の見直しと財源について
◎河合喜代議員
質問の第1は、2025年度予算編成方針についてです。
まず、地方財政に関わる税制の見直し論議についてです。
周知の通り、自公政権と協議されている国民民主党の減税案は、「所得税の課税最低限」を103万円から178万円に引き上げるもので、政府の試算では7.6兆円の財源が必要となります。財源をどこに求めるかによっては、かえって負担増になる人が出る場合も考えられます。「課税最低限」の見直しと、そのための財源について県の見解を伺います。
●村岡嗣政知事
私からは「課税最低限」の見直しと財源についてのお尋ねにお答えします。
いわゆる「103万円の壁」の引上げについては、働き控えの解消や手取りの増加につながることが期待されるとともに、恒久的な歳入減となるため、その財源確保対策が必要となります。
こうした中、国において、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が決定され、「103万円の壁」について、令和7年度税制改正の中で議論し引き上げることとされています。
私は、「103万円の壁」の引上げに当たっては、国において、あるべき政策と恒久的な財源をセットで丁寧に議論が進められることが重要であり、その中で、住民に身近な行政サービスを担う自治体の財政運営に支障がないよう、対応されるべきと考えています。
2、最低賃金の引上げについて
◎河合喜代議員
わが党も先の総選挙の政策で「課税最低限の引上げ」を掲げました。課税最低限が103万円になったのは1995年ですが、その当時と2023年の物価を比べると10%以上も上がっています。物価上昇に見合う程度の引上げなら、その財源は税の自然増収分の一部を還元することで確保でき、財源の心配も要らないという提案です。
いま必要な第1は、最低賃金を速やかに時給1500円に引き上げることです。そうすれば年収は150万円になり、保険料や税金を差し引いても手取りは大幅に増え、「壁」を乗り越えられます。
●高林謙行産業労働部長
2025年度予算編成方針についてのお尋ねのうち、最低賃金の引上げについてお答えします。
最低賃金については、法律に基づき、各地域の労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して、国が設置する最低賃金審議会の審議を経て、地域の労働局長が決定するものです。
その額については、最低賃金審議会を構成する公益。労働者・使用者の代表によりしっかり議論され、適切な水準に設定されるものと考えております。
◎河合喜代議員
第2に、低所得者の社会保険料を軽減することで「壁」の高さを下げることです。特に協会けんぽと比べ2倍も高い国民健康保険料の引き下げが急務です。国保財政に1兆円の予算を追加して、国保料を下げるべきです。
●國吉宏和健康福祉部長
国民健康保険料についてお答えします。
国民健康保険などの社会保険制度については、その負担のあり方を含め、国の責任において十分な議論のもと制度設計されるべきものであり、県としては、将来にわたって安定した制度となるよう、これまでも、全国知事会等を通じて、国に要望しているところです。
◎河合喜代議員
議会初日の議案説明において知事は、来年度の当初予算編成について、人口減少対策を喫緊の課題にあげ、その第1に「若い世代や女性の声に的確に応える」ことをあげました。
私たちは、結婚するか、子どもを持つかについては個々人の選択に委ねられるものと考えます。その上で政治が果たすべきは、誰もが安心して結婚し、子どもを持ち、育てられる経済的、社会的基盤を用意することだと考えます。
県内の婚姻数は、2002年は7503組でしたが、22年は4593組と約4割減っています。一方、出生数は2002年は12578人、22年は7762人です。単純ではありませんが、1組のカップルから生まれる子供の数は1.6~1.7人で推移しています。婚姻数が増えることで出生数は増加するという認識で間違いないでしょうか。お尋ねします。
●國吉宏和健康福祉部長
次に、出生数の増加についてです。
我が国では、出生する子どものほとんどが婚姻関係にある男女の嫡出子となっており、出生数を増やすには、婚姻数を増やすことが有効であると考えます。
◎河合喜代議員
今年度、県が実施した「若者や子育て世帯に対する県民実感度調査」で「子どもを産み、育てやすい環境づくりに向け、山口県に力を入れてほしい取り組みは何ですか」との問いのトップは「医療費や保育料など子育て世帯の経済的負担の軽減対策」、2番目は「教育費に対する支援の充実」です。子ども医療費や学校給食費に対する助成制度の地域間格差解消のために県が一歩踏み出すことが必要ではないですか。お尋ねします。
●國吉宏和健康福祉部長
子ども医療費に対する助成制度についてです。
本県の乳幼児医療費助成制度は、国の医療保険制度を補完し、一定の福祉医療の水準を確保することを目的として、基準を定めて助成しているものであり、将来にわたって持続可能な制度とするため、現行水準を維持することが基本であると考えています。
◎河合喜代議員【再質問】
子どもの医療費については、全く9月と同じ一言一句変わらない判子で押した答弁で、これではやらない理由にもなっていないのではないかと。これほど子供が少なくなってどの自治体も危機感を持って、知事もだから人口減少対策を掲げられています。それなのに、もう先ほど紹介した、去年ね、意見聴取しておられます。この中で市町からの意見を聞いておられるんですけれども、その中に市町からの提案としてね、子どもの医療費、学校給食費の無償化、そして保育料の負担軽減というのが入っているわけですね、保育料の負担軽減はやられました。だけれども、この子どもの医療費と学校給食費については、どのような検討をされたのでしょうか、お示しください。
少子化対策は今本当に、あらゆる取組が求められているんですけれども、その中でも市町からね、このやっぱり子ども医療と学校給食費を取り組もうよということをやられて提案されて、市や町も取り組んでいるわけですね。もう19市町中4市町以外は全部が高卒まで子ども医療費を無料にしましたし、その4市町だって中学卒業まで対象を拡大しています。県だけがこの同じ判子でついた答弁で、一定の福祉医療の水準を確保することを目的として助成しているんだと。完全に傍観者じゃないですか。こういう態度で良いのかということが問われているんじゃないですか、
見解をお伺いします。
●國吉宏和健康福祉部長
子ども医療費助成に関して、県は何もせず傍観するのかというようなお尋ねでございました。
繰り返しになりますけども、本県の制度は、国の医療保険制度を補完し、一定の福祉医療の水準を確保することを目的として、基準を定めて助成しているものであり、将来にわたって持続可能な制度とするため、現行水準を維持することが基本であると考えています。
なお、子ども医療費の助成については、県の市長会において、国における全国一律の助成制度の創設を要望されていることも踏まえ、県としても、全国知事会等を通じてその旨、国に要望しているところです。
●根ケ山副教育長
学校給食費に対する助成制度についてです。
学校給食費の助成制度については、設置者が実情に応じて判断することが基本と考えてお叺現時点、お示しのような対応は考えていません。
◎河合喜代議員【再質問】
去年、意見聴取しておられます中で、市町からの意見を聞いておられるんですけれども、その中に市町からの提案としてね、子どもの医療費、学校給食費の無償化、そして保育料の負担軽減ていうのが入っているわけですね。保育料の負担軽減はやられました。だけれども、子どもの医療費と学校給食費についてはどのような検討をされたのでしょうか。お示しください。少子化対策は今ほんとにあらゆる取り組みが求められているんですけど、その中でも市町からね、このやっぱり子ども医療費と学校給食費を取り組もうよということをやられて提案されて市も町も取り組んでいるわけですね。
それから、学校給食については、金額が多額になるということでしたかね。教育長が答弁してくださりましたかね。またここも私はちょっと聞き漏らしているのかもしれないですけれども、これも今紹介しましたが市町からそういう声が上がっています。どういう検討を市町からの意見聴取をしてどういう検討をされたのかお聞きします。そしてですね、もう1点は、給食費の無償化については、憲法が「義務教育は無償とする」と、このように明文化をしています。国会答弁でも給食費をこの義務教育の無償化の対象として想定しています。憲法の実現に自治体も努力する時が来ていると思います。憲法の「義務教育は無償とする」との条文を知事と教育長はどう受け止めておられますか。お尋ねをいたします。
●根ケ山副教育長
河合議員の再質問にお答えします。
学校給食費について、市町からの施策提案についてのお尋ねでしたが、少子化は日本全体の課題であり、学校給食制度に地域間格差が生じないよう、全国都道府県教育長協議会等、協議会等を通じ、引き続き国に対応を要望したところでございます。
また義務教育は無償化でないかということに関してのお尋ねであったかと思いますけれども、学校給食法では給食の実施に必要な施設、設備及び運営に要する経費以外は保護者負担とされているところであります。国においては現在骨太の方針などで、「学校給食無償化の課題整理等を行う」とされているところであり、国の動向を注視していきたいというふうに考えております。
◎河合喜代議員【再々質問】
学校給食なんですが、学校給食法で食材は保護者負担となっていますけれども、それを自治体が負担することは妨げないというのも国会答弁となっています。だから、今、全国で学校給食が広がっていますし、先日の自民党総裁選でも茂木さんが学校給食をぜひ実現したいとこのようにおつしやったんではなかったでしょうか。この点でも全国の自治体が今これに恥組んでいます。ここのところの認識は改めるべきだと思いますがいかがでしょうか。
●根ケ山副教育長
河合議員の再々質問にお答えします。
給食費の学校給食の市町の支援を妨げるものではないのではないかということでありますけれども、市町の学校給食費の無償化については設置者が実情に応じて判断するのが基本であると考えております。
◎河合喜代議員
県は「子育て世帯への住宅支援」についても「検討を進める」と言われています。新築世帯には税額控除がありますが、住宅を購入できない世帯への支援として、市町から提案されている「公営住宅の活用」は有効です。
県が今年度からはじめた県営住宅を活用した「お試し暮らし住宅」もよいですが、県内に住んでいる子育て世帯への県営住宅の入居は、経済が厳しい今こそ期待されている施策だと思います。県外からの移住者にはリノベーションをして県営住宅にお試し暮らしを薦めているのですから、県内に住み、税金を納め、子どもを育てる世帯に住宅支援するのは大事なことではありませんか。また、現在の県営住宅はどこも老朽化しています。公営住宅法に掲げる「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の整備」の立場で、経年劣化した住宅の必要な屋内改修は県が責任を持つべきですが、県の見解を求めます。
●大江土木建築部長
公営住宅の活用についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、子どもを育てる世帯への住宅支援についてです。
県営住宅の入居者募集に際しては、多子世帯や母子.父子世帯を優先入居の対象とするなど、子育て世帯の入居について配慮しているところです。
次に、経年劣化した県営住宅の屋内改修についてです。
県では、構造上重要な部分など、管理者として修繕すべき部分において、必要な場合は、適切に修繕を行うこととしています。
2025年度施策重点化方針について
◎河合喜代議員
質問の第2は、2025年度施策重点化方針についてです。
同方針では、第1に社会減対策として「人手不足対策」があげられ、2026年度における必要な人員を試算されています。
医師の必要人員は3519人とされ、2020年の3491人と比較すれば28人増で足りますが、医師の高齢化、産婦人科・小児科医師の不足は深刻です。どう取り組まれるのでしょうか。
介護分野では、2026年に2749人、2040年には2816人の不足が見込まれています。県は「介護職員処遇改善加算の取得割合が全国平均より低いため、加算の取得による処遇改善のいっそうの推進が必要」としています。加算の取得が低い原因は何か、処遇改善と職員増にどう取り組んでいかれますか。
保育分野では、今年4月1日時点で、保育士の必要見込み数と常勤換算後の保育士の現員を比較すると221人不足しています。どう解消する計画ですか。
また、現行の配置基準で、ゼロ歳児は保育士1人に対し乳児3人であり、「災害時には2人は前と後ろに抱えて避難できるが、3人はできない」との声があります。不足人員を超える保育士の確保が必要と考えますが、いかがですか。
●國吉宏和健康福祉部長
県では、「山口県医師確保計画」に基づき、地域医療の充実を図るため、本県の医療を担う若手医師の養成・確保に向けた対策に取り組んでいるところです。
また、産婦人科・小児科医師については、医師修学資金に県内医療機関で両診療科の医師として勤務することを償還免除要件とする貸付枠を設けるなど、その確保に努めているところです。
次に、介護分野の2点についてお答えします。
まず、加算の取得割合が低い原因は何かとのお尋ねについては、事業者からは、事務作業の煩雑さや制度の複雑さなどの声を聞いています。
次に、処遇改善と職員増にどう取り組んでいくのかとのお尋ねについては、事業所の管理者向けの研修、社会保険労務士などの専門的な相談員の派遣等を通じて、介護職員等処遇改善加算の取得を促進するなど、介護人材の確保に取り組むこととしています。
次に、保育分野の2点について、まとめてお答えします。
お示しの221人については、令和4年度に算定した必要見込数と現在の保育士数を常勤換算したものの差であり、不足している数ではありません。
各保育所においては、配置基準を満たした上で運営されていますが、現場における保育士の不足感を踏まえ、県としては、保育士修学資金の貸付けや、潜在保育士の再就職支援など、引き続き、保育士確保の取組を進めてまいります。
◎河合喜代議員
公共交通の要でもあるバス・タクシーの運転手の不足も問題化していますが、必要な人数はそれぞれ何人と推計されていますか。
県は自動運転を推奨していますが、基本は人ではないでしょうか。自動運転は時速も遅く、路線も利用者も限られます。脱炭素社会のためにも公共交通の拡充は不可欠であり、必要な運転手を確保することは不可欠と思います。バス運転手の労働時間は全産業平均より月10時間長く、賃金は月約5万円安いことなどを改善することが必要と考えます。運転手の確保にどう取り組んでいかれますか。
●道免憲司観光スポーツ文化部長
バス・タクシー運転手についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、バス・タクシー運転士の必要な人数についてですが、山口労働局によると、9月時点の有効求人数は、バス運転士は84人、タクシー運転士は635人となっています。
次に、運転士の確保への取組については、今年度、国や関係団体等による協議会を設置し、課題の共有や対策の検討を行いながら、就職フェアの開催など、県内外から運転士を確保する取組を実施しているところであり、引き続き、関係者と連携しながら取り組んでまいります。
◎河合喜代議員
加えて農林漁業の衰退は、県民の命綱である食料にかかわる問題です。農業、林業、水産業を支えるために必要な従事者数、生産量の目標を明確にして、対策を強化することが必要ではありませんか。お尋ねします。
県自身、社会減対策として「成長エンジンとなる産業力の強化」で、「食料の安定供給の確保等に向けた強い農林水産業の育成」を掲げておられます。国に対し、農林水産物の所得補償と価格保障制度の創設を提言することは不可欠と思います。見解を問います。
予算編成に係っては、多くの自治体が編成過程の「見える化」に取り組んでいます。事業ごとの要求額と部内での査定結果、知事査定の結果等を公表することです。自治体DXの取り組み強化に取り組んでいるのですから、その一環としても「見える化」を推進して県民への説明責任を果たすべきと考えますが、伺います。
●大田淳夫農林水産部長
まず、農林水産業における目標と対策の強化についてです。
県では、「やまぐち農林水産業振興計画」において、生産性と持続性を両立した強い農林水産業の育成を基本目標に掲げ、様々な取組を進めているところです。
この計画において、従事者については、農業中核経営体数や農林漁業の新規就業者数などの目標を、生産については、県オリジナル品目の生産量や木材供給量などの目標を定め、これらの目標達成に向け、担い手の確保・育成や生産対策等に取り組んでいます。
次に、農林水産物の所得補償と価格保障制度の創設の国への提言についてです。
農林水産物の所得補償や価格保障制度については、国において検討されるものと考えており、その創設について、国に提言することは考えていません。
◎河合喜代議員
予算編成に係っては、多くの自治体が編成過程の「見える化」に取り組んでいます。事業ごとの要求額と部内での査定結果、知事査定の結果等を公表することです。自治体DXの取り組み強化に取り組んでいるのですから、その一環としても「見える化」を推進して県民への説明責任を果たすべきと考えますが、伺います。
●佐藤茂宗総務部長
予算編成過程の「見える化」についてのお尋ねにお答えします。
編成過程の「見える化」については、各自治体が各々の判断で行っているものであり、本県では、予算編成はあくまで意思形成過程であることから、要求額等は公開していませんが、決定した予算案については、これまでも、県のホームページ等を通じて、できるだけ詳しく公表をしてきたところです。
県としては、今後も、予算の内容をわかりやすく公表するとともに、県議会において御審議をいただくことによって、県民の皆様への説明責任を果たしてまいりたいと考えております。
介護保険制度について
◎河合喜代議員
質問の第3は、介護保険制度についてです。
今年4月以降、全国で訪問介護事業所の倒産・廃業が相次いでいます。県内でも訪問介護事業所は今年4月から11月までに新規9に対し、休廃止14で差し引き5事業所減少しています。4月からの訪問介護サービスの報酬引き下げが影響しています。
合併前の旧市町村単位で見ると資料1のように6地域は訪問介護サービス事業所が空白になり、13地域は1つだけになっています。
事業所にとっては、遠方まで訪問してサービスを提供すると採算が合わず、訪問介護を受けて自宅で暮らしている高齢者等が、訪問介護サービスを受けられなくなり、やむを得ず入所施設に移らざるを得ないケースも聞きます。同じ保険料を負担しても、住む場所によってサービス利用できないなど「保険」に値しないのではありませんか。お尋ねします。
これ以上、訪問介護サービス空白の地域を広げないためにも、国に対し、訪問介護の報酬引き上げを働きかけるべきです。見解をお尋ねします。
●國吉宏和健康福祉部長
介護保険制度については、その給付と負担の在り方を含め、国の責任において十分な議論の下、制度設計されるべきものと認識していることから、県としては、将来にわたり安定した制度となるよう、これまでも国に要望してきたところです。
◎河合喜代議員【再質問】
訪問介護報酬については、引き上げを求めるように、国に求めてほしいということを質問したと思いますけれども、ちょっと私が答弁を聞き漏らしたのかもしれませんが、もう一度お願いをしたいと思います。
●國吉宏和健康福祉部長
介護保険制度につきまして、訪問介護事業所が運営できるような介護報酬でなければならず、国に要望するつもりはないのかというところでございますが、先ほども答弁させていただきましたとおり、介護保険制度は国の責任において制度設計されるべきものであるということから、県としては将来にわたり安定した制度となるよう、これまでも国に要望してきたところであります。
◎河合喜代議員【再質問】
それから訪問介護の報酬について、来年3月に国は調査結果をまとめて、って言っていますけれども、これはもう都会と、やっぱり僻地との格差なんですよね。周辺部では訪問介護事業が事業として成り立っていないわけですよね。だから、作れない。そもそも先ほど示しましたけれども、旧市町で言うとゼロだったり、1ヶ所しかない。そうすると、もうそれでなくてもヘルパーがいないから受けたいサービスが受けられない、施設に入るにはお金がいる。お金がない人は在宅で1人でいるか、老老介護に甘んじるか、っていうか苦労するか、そういう選択肢しかなくなっていくわけです。もう2000年に介護保険が始まって、皆さんからたくさん保険料をかけてもらっています。なぜこういうことが起こるのか、根本的に見直さなければならないのではないでしょうか。この介護保険制度が保険あって介護なしということにならないように、先ほど部長は、国が制度設計するもので、安定した制度となるよう要望してきたと言われましたけれども、目の前も安定していないじゃないですか。使いたいサービスが、事業者がないじゃないですか。これについて、県として国にどう何をどう改善を求めていくのか考えをお示しください。
●國吉宏和健康福祉部長
介護保険制度につきまして、保険あって介護なしではないかというようなお尋ねでございましたけれども、訪問介護事業所がサービスを提供する範囲は、事業所が所在する旧市町村単位の範囲に限られるものではないということでございまして、これまでも地域の実情に応じ、サービスが提供されてきたというふうに認識しております。
介護保険制度は、国の責任において制度設計されるべきものであることから、県としては、将来にわたり安定した制度となるよう、国に要望してきたところです。
県といたしましては、県といたしましては、個別の介護サービスに係る報酬につきまして、国に要望することは考えておりません。
◎河合喜代議員【再々質問】
訪問介護事業所は旧市町にこだわらず提供されていると。誰もこのサービスから漏れていませんか。そうはっきり言えますか。お尋ねします。
●國吉宏和健康福祉部長
訪問介護において、誰もサービスが漏れていないかという再々質問でございました。
これまでも、地域の実情に応じ、サービスが提供されてきたところであり、今後も、サービスが提供されるものと認識しています。
教育現場の現状と課題について
◎河合喜代議員
質問の第4は、教育現場の現状と課題についてです。
資料2の通り、県内でも小中高校でも不登校の児童生徒数は激増しています。2019年度と23年度の出現率を比較すると、小学校は2.8倍、中学校は1.8倍、高校も1.4倍です。
文科省は増加の背景には、令和5年度は新型コロナウイルス感染拡大で生活リズムが乱れたことによる登校意欲低下や、休養の必要性について保護者の意識が変化したことなどがあげられるとしていますが、県教委としては、どのようにお考えか、お尋ねします。
教育問題では、この間、県内でも相次いでいる教師の不祥事についてです。あってはならない残念な事件が後をたたない現状をどう受け止め、どのように対処されるのか、お尋ねします。
●繫吉健志教育長
不登校の児童生徒数の増加の背景についてです。
県教委では、文部科学省の分析と同様、コロナ禍の影響による登校意欲の低下などがあると考えています。
次に、教師の不祥事についてです。
県教委としましては、児童生徒の手本となるべき教員が続けて逮捕されたことを重く受け止めており、市町教委と連携し、県内全ての公立学校の教職員に対して綱紀保持の徹底を図り、あらゆる不祥事の根絶と公教育に対する県民の信頼回復に取り組んでいくこととしています。
◎河合喜代議員
学校は本来、子どもにとっても先生にとっても楽しい場所であるはずだと思いますし、そうあってほしいとみなが願っているのではないでしょうか。学ぶこと、知ること、友だちとつながることは楽しいことのはずです。先生も教えること、子どもたちの成長を日々目にすることは本来喜びのはずです。なぜそうなっていないのでしょうか。
子どもの不登校が増え続けている根本的な背景には、国連が指摘するように、全国学力テストなどによる過度な競争で子どもたちを比べ競わせる、そして。子どもたちを管理の対象とする教育が学校に押し付けられてきたことがあるのではないでしょうか。
子どもたちが通いたくなる学校にするためには、この競争と管理の教育を根本的に見直すことが最優先課題です。具体的には、県が実施している学力調査は中止し、先生を増やして、早期に30人以下学級を実現することだと考えますが、見解を尋ねます。
そして、①「子どもの権利条約」の精神を生かし、子どもが安心して休む権利、自分らしく生きられる権利を大切にする、②子どもと親が不登校にかかわるさまざまなことを相談できる窓口を拡充する、③子どもの居場所として学校復帰を前提としない公的施設を拡充する、④フリースクール・フリースペースなどをきちんと認め、公的支援を行う、⑤不登校の親子を支えあう「親の会」などへの公的支援を行う、ことなどが大切だと考えます。それぞれ見解を問います。
また、NGО団体である「新日本婦人の会」が先月、実施した「不登校についての緊急アンケート」で気付かされた1つは、子どもが家にいるために親が働けない「不登校離職」です。2つに、子どもが日中家にいるため食費やフリースクール利用料などで出費が増えるなど経済的負担です。「学校に行っていない間はせめて学校給食費は免除してほしい」との声は切実です。フリースクールに通うための交通費や学校に行っていない間の学校給食費の免除になる経済的な支援策を検討することも必要と考えますが、伺います。
●根ケ山副教育長
次に、教育現場の現状と課題に関する御質問のうち、不登校の現状と対応についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、学校が楽しい場所になっていないとのお尋ねですが、県教委では、市町教委と連携しながら、子ども自身が成長を実感したり、教員がその手応えを感じたりできる学校づくりを支援しているところであり、御指摘は当たらないと考えています。
次に、不登校が増え続けている背景については、コロナ禍の影響による登校意欲の低下などがあると考えており、過度な競争や押し付けという御指摘は当たらないと考えています。
次に、県の学力調査については、子どもの学力状況を把握し、その確実な定着と向上を図ることを目的として実施しており、中止することは考えていません。
また、30人以下学級の実現については、国の財源措置が図られない中、県独自財源で進めることは困難です。
次に、子どもの休む権利、自分らしく生きられる権利についてですが、誰もが安心して学ぶことができるよう、まずは、学校教育の充実に取り組むことが重要と考えています。
次に、不登校についての相談窓口については、電話による「24時間子どもSOSダイヤル」やSNS等を活用した相談窓口を設置しているところです。
次に、子どもの居場所としての公的施設についてですが、県教委としては学校復帰を目的とした校内教育支援センター等の学びの場の確保に努めているところです。
次に、フリースクールなどについては、不登校等児童生徒の居場所の一つとして考えられますが、校内教育支援センター等の学びの場の確保に努めているところであり、お示しの公的支援は考えていません。
次に、「親の会」などへの支援についてですが、不登校児童生徒や保護者に対しては、例えば、家庭教育支援チームと学校等との連携による支援体制の構築に取り組んでいるところであり、お示しの公的支援は考えていません。
次に、フリースクールに通うための交通費についてですが、学校内での学びの場の確保に努めているところであり、支援は考えていません。
また、学校給食費については、長期欠席になる場合には、保護者の意向に応じて、減額する対応も行われているところです。
県教委としましては、全ての児童生徒の学びの保障に向けて、引き続き、不登校対策に取り組んでまいります。
◎河合喜代議員【再質問】
競争と管理の教育という指摘は当たらないとのことだが、テストはやはり競争に子どもたちを追い立てる。これが、全国でも行われ、県でも行われる。こういうことが本当に必要なのか、ということを私は間うている。青森県では昨年度県のテストをやめている。やはり、子どもたちや先生たちを本当に開放していく、そういうことが今本当に必要なのではないか。そのことを切に思うので、もう一度、見解を伺う。
●根ケ山副教育長
国や県のテストが本当に必要なのかということであったかと思いますが、国や県が行う学力調査は、子どもの学力状況を把握し、学力の確実な定着と向上を図ることを目的としており、競争管理を行うために実施しているものではございません。
今後も、継続して実施することで、しっかりと課題を把握し、学習指導の工夫改善を進め、学校の学力課題を解決してまいりたいというふうに考えております。
◎河合喜代議員【再々質問】
学力調査については競争のためにしているわけではないとのことだが、結果的には競争となっている。やめるべきだ。子どもたちを自由に、本当に喜べる学校にしてほしいと思う。この点について、 もうー言、答弁を求める
●根ケ山副教育長
結果的に競争になっているのではないかということでありますけれども、県教委としてはあくまでも子どもの学力状況を把握し、学力の確実な定着と向上を図ることを目的としていることで、そういうテストでありますので、競争管理を行うために実施しているものではございません。
岩国基地の機能強化について
1、新たな艦載機部隊の配備について
◎河合喜代議員
質問の第5は、岩国基地の機能強化についてです。
米海軍横須賀基地を母港とする米原子力空母の交代に伴う新たな艦載機部隊の岩国基地への配備が11月17日、完了しました。
1つは、米海軍等の報道によると、資料3の通り、岩国基地配備の新たな第5空母航空団はCМV22オスプレイ4機、F35Cステルス戦闘機14機に加え、FA18スーパーホーネットの3つの戦闘攻撃飛行隊・計36機、EA18Gグラウラー電子戦機飛行隊6機、E2D早期警戒飛行隊5機の計65機となります。これまでより4機増加することになり、住民生活への影響が危惧されますが、どう認識されていますか。お尋ねします。
●田中康史総務部理事
岩国基地の機能強化についての数点のお尋ねにお答えします。
まず、岩国基地への新たな空母艦載機部隊の配備に伴う住民生活への影響に関する県の認識についてです。
国からは、「岩国飛行場配備の空母艦載機の機数については、F-3 5C及びCMV-2 2を含め約60機」との説明を受けており、機種更新前と大きな変動はないことなどから、このたびの機種更新等については、基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではないと考えています。
◎河合喜代議員
2つに、看過できないのは国内では初配備となるCМV22と同型機であるオスプレイの事故・トラブルが頻発していることです。
米軍普天間基地所属のМV22オスプレイは11月14日、奄美空港に緊急着陸、21日にはCМV22オスプレイが同空港に緊急着陸しました。いずれも「飛行中に警告灯が点灯したため予防着陸した」と説明されています。
自衛隊のV22オスプレイも10月23日、何らかのトラブルで鹿屋航空基地に緊急着陸。同27日には、与那国駐屯地で離陸に失敗し、機体を損傷しました。
こうした事故・トラブルの原因と再発防止策について米軍や自衛隊はどのように説明しているのか、お尋ねします。
●田中康史総務部理事
次に、オスプレイの事故・トラブルの原因と再発防止策に関する米軍や自衛隊の説明についてです。
お示しの米軍のMV-2 2及びCMV-2 2の奄美空港への予防着陸について、国からは、「予防着陸は、安全確保の手段の一つと承知しているが、米軍機の運用に際しては、安全の確保が大前提と考えており、引き続き米側に対し、安全管理に万全を期すよう求める」との説明を受けています。
また、自衛隊のV-22について、国からは、「鹿屋航空基地への着陸は予防着陸であり、異常の有無等を確認後、翌日に離陸した。与那国駐屯地で発生した航空事故については、事故原因は人的要因であり、訓練の充実などの各種の再発防止策を図る」との説明を受けています。
◎河合喜代議員
3つに、岩国基地に配備されたCМV22は日常的に訓練飛行を行うだけでなく、空母出港前にはFCLPのための事前訓練も実施するのではないかと考えます。日常的な訓練ルート、事前訓練の有無について明らかにすべきですが、お尋ねします。
●田中康史総務理事
次に、岩国基地に配備されたCMV-22の日常的な訓練ルート、FCLPのための事前訓練の有無について明らかにすべきとのお尋ねです。
国に照会したところ、「今回の機種更新により、これまでの岩国飛行場周辺の飛行経路に変更はなく、日々の運用が大きく変わるものではない。今後、米側から公表可能な情報が得られ次第、速やかに情報提供する」との回答を得ています。
いずれにしましても、県としては、引き続き、地元市町と連携し、配備後の航空機の騒音や運用などの実態把握に努め、問題があれば、国や米側に必要な対応を求めてまいります。
◎河合喜代議員【再質問】
岩国基地の問題は、大きな影響はないと言われています。
だったらなおさらのこと、オスプレイはC2輸送機の機種変更であります。C2輸送機についてはコンターを、騒音コンターを示しております。騒音コンターを示させるべきではないですか。違いがないと言うのなら、そうやって住民の安心をちゃんと一つ一つ県が作っていく、示していくということが必要ではありませんか。
それからオスプレイは、警告灯が点灯したために緊急着陸したと。安全管理に万全を期すように要望しているとおっしゃいましたけれども、そもそもなぜ警告灯が点灯するのでしょうか。その原因はなんだと説明されているのですか、これほど緊急着陸を繰り返す機体が他にありますか、こうした欠陥品は返品するべきではありませんか。もうこんな怖いものを県民の頭の上で飛ばさないでくださいよ、と私は思いますよ。県の見解をお尋ねします。
●田中康史総務理事
岩国基地に関する再質問にお答えいたします。
まず最初に、空母艦載機移駐の際に騒音予測コンターが示されているので、今回も騒音予測コンターを求めるべきとのお尋ねだったと思います。
国の説明によりますと、今回の機種更新等については、機数が減少し、平素の運用に大きな変更は生じないことから、騒音予測コンターを作成する必要性は少ないとのことであり、コンターは示されませんでしたが、空母艦載機の機数に大きな変動はなく、また、海兵隊機の機数が10機程度減少することから、岩国基地の一日の標準飛行回数が今より増えることは見込まれず、また、岩国基地周辺の飛行経路に変更はなく、日々の運用が大きく変わるものではないことなどから、岩国基地周辺の騒音状況については、現在より拡がらないと見込まれると整理したところです。
次に何度も警告灯がつくようなオスプレイについては、飛ばさないでほしいといった質問だったかと思います。
県としては、オスプレイを含む航空機の安全性については、専門的な知見を有する国の責任において確保されるべきものと考えています。国としては、オスプレイの安全性については、これまでも累次の機会に確認しており、問題は
ないとのことであり、そうしたことを求める考えはございません。
2、空母ジョージ・ワシントンの洋上視察について
◎河合喜代議員
4つは、米空母ジョージ・ワシントンの洋上視察についてです。
空母艦載機の岩国基地への帰還が始まっていた先月10日、山口県の岩国県民局長は、岩国市の福田良彦市長や中国四国防衛局の田實博幸局長らと共に、岩国基地からCМV22オスプレイに搭乗して米空母ジョージ・ワシントンの洋上視察に参加しました。オスプレイなど機体の安全性への疑問や不安、騒音被害の拡大を懸念する住民感情を逆なでする行為とは考えなかったのでしょうか。お尋ねします。
当日は、11時半に出発、13時半に空母に着艦し、同空母のウェイツ艦長の案内で格納庫など艦内の説明を受け、甲板上ではF35Cも視察しました。県に確認したところ、県民局長は公務として参加し、艦内では「コーヒーと肉料理」が提供されました。
山口県職員倫理規程の第1条は「職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする」として、「禁止行為」として第4条第1項第4号に「利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること」、第7号に「利害関係者と共に飲食をすること」をあげています。その上で、「例外」として、「職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること」としています。
倫理規程に照らして、今回の洋上視察に参加したことは何の問題もなかったのか、お尋ねします。
●田中康史総務理事
次に、空母ジョージ・ワシントンの洋上視察への参加は、住民感情を逆なでする行為とは考えなかったのかどのお尋ねです。
今回の視察については、県民の安全で平穏な生活を確保する立場にある県として、新たに配備されるF-3 5C及びCMV-2 2を含む空母艦載機の運用等の実態把握に向けた情報収集のために参加したものであり、御指摘は当たらないと考えています。
次に、倫理規程に照らして、今回の視察への参加に問題はなかったのかとのお尋ねです。
今回の視察は、国からの案内を受け、県民局長が公務として参加したものです。
また、他の参加者とともに軽食の提供を受けた行為は、倫理規程上、禁止行為から除外されている「職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること」に該当することから、視察への参加に問題があったとは考えていません。
農業試験場跡地の利用策について
◎河合喜代議員
質問の第6は、農業試験場跡地の利用策についてです。
市民団体「山口市有機・環境保全型農業公園を造る会」は先月18日、山口県と山口市に対し、有機農業に親しめる農業公園を造るよう求める要望書を2647筆の署名とともに提出されました。
「造る会」は、「ハウスや田んぼを活用して建設費を抑えられる。みんなで造る農業公園を目指したい」と話されています。
跡地の利用策については、山口商工会議所を含め、県民からさまざまに意見が出されています。そこで要望したいのは、①基本計画を急ぐことなく、じっくりと市民の意見を聞く時間を保証すること、②県と山口市でつくる検討協議会をオープンにして誰もが傍聴できるようにすることです。見解を求めて、第1回目の質問とします。
●永富直樹総合企画部長
農業試験場跡地の利用策についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、市民の意見を聞くことについてです。
まちづくりに当たっては、地域の実情や住民のニーズ等を最もよく知る地元自治体の主体的な判断が重要となります。
このため、市民からの意見については、地元山口市において把握いただき、市のまちづくりとの整合性を踏まえながら十分に検討を行っていただくこととしております。
その結果を踏まえ、県・市による検討を進めてまいります。
次に、検討協議会の傍聴についてです。
協議会の会議においては、その後の事業の推進などに支障がないと認められる部分については、会場の受け入れ可能人数の範囲内で傍聴可能としているところです。
なお、会議内容については、協議会の終了後、ホームページに会議内容を掲載するなどして、できるだけ速やかに情報提供を行うよう、努めています。
◎河合喜代議員【再質問】
農業試験場については、今年3月の検討協議会の資料の今後のスケジュールによると、今年10月に基本計画策定の予定でした。今まだできておりません。現時点で基本計画策定の時期はいつを目指しているのか、明らかにしてください。そして、検討協議会はいつ開かれる予定ですか、お示しください。
それから、2020年、令和4年の11月の基本構想素案の今後の事業の進め方によると、今年年内くらいに民間活力導入に向けた検討を終え、最適事業手法の検討、募集要項整理、来年度初め頃までに都市計画の見直し等を終え、来年度半ばに事業者選定、再来年度建設開始となっています。
現在、基本計画以外のこれらの取組はどこまで進んでいるのですか、進んでいないのですか。いつ頃に延期、変更をしているのですか、していたらお示しください。
●永富直樹総合企画部長
農業試験場跡地に関する再質問にお答えします。
まず、基本計画の策定のスケジュールについてでありますけども、現在、県と市で基本計画の素案の取りまとめに向けて検討を行っているところであります。策定のスケジュールは、その検討状況によって変わってまいりますので、現時点では未定でございます。したがいまして、2つ目の質問でありました協議会の開催時期についても未定です。
それから、基本構想で示した取組についての進捗状況ということでありますけども、現在、基本計画の策定に向けて県と市で検討を進めているという状況でありますので、お尋ねのありました取組につきましては、そうした検討の後に整理をしていくということとしております。したがいまして、これについても、時期についてはまだ未定でございます。
(2024年12月3日)