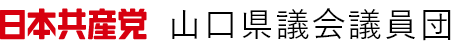核兵器禁止条約について
◎木佐木大助議員
質問の第1は、核兵器禁止条約についてです。
核兵器の非人道性を根拠に核兵器の開発、製造、保有、使用を禁じる核兵器禁止条約は、発効から4年目を迎え、その威力を発揮しつつあります。
1つは、核兵器の使用をタブーとする風潮を強め、核保有国に対しても核兵器の削減と廃絶への圧力となっていること、2つに、核兵器を製造・生産・保有する国への支援を禁止するため、核兵器製造に関わっている会社への投資を止める企業が増えていること、3つに、核保有国による核使用の手をきつく縛り、核兵器固執の最悪の拠り所となっている「核抑止力」論を打ち破るうえで大きな規範力が働き始めていることなどです。
こうした「威力」について、知事はどう認識されていますか。お尋ねします。
自公政権は、世界で唯一の戦争被爆国でありながら、「核抑止力」にしがみつき、核兵器禁止条約の批准を拒み続けています。こうした中、同条約制定に貢献したNGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN(アイキャン)などが運営する「議員ウオッチ」の調査によると「日本は批准すべき」という意思を示している政治家は、資料1のように、知事17人のほか、国会議員は計709人中257人にのぼり、自民党27人、公明党48人も含まれています。また、批准を求める意見書、決議を採択した地方議会は687と、全1788議会の38%を占めるまでになっています。
日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める世論は確実に広がっていますが、残念なことに県内の19市町で批准を求める意見書、決議を採択した議会はゼロです。
こうした状況を打開するためにも、知事が率先して核兵器禁止条約の批准を求める立場に立つことが重要と考えます。伺います。
なお資料4は、1995年に本会議に提出された要望決議案です。
●村岡嗣政知事
木佐木議員の御質問のうち、私からは、核兵器禁止条約についてのお尋ねにお答えします。
核兵器禁止条約は、核兵器廃絶を求める多くの国・地域の人々の思いや行動等により発効に至ったものであり、核兵器を世界全体でなくしていこうという機運の醸成に繋がるものと認識しています。
一方、この条約に関しては、政府は以前から、核兵器廃絶という目標は共有するものの、この条約には参加することなく、核兵器国と非核兵器国の協力の下に現実的・実践的な取組を行うこととしています。
私は、核兵器の廃絶自体は、これを強く願っているところですが、そのための手法については、国の専管事項である安全保障とも密接に関わっていることから、国民の命と平和な暮らしを守る観点で、国において、しっかり検討を進めていただきたいと考えています。
こうしたことから、私としては、あくまでも国の取組を尊重する立場に立って、国に対し核兵器禁止条約への批准を求めることは考えていません。
◎木佐木大助議員《再質問》
知事は、自分も核廃絶は喫緊の課題と言いながらも、国の立場を尊重するという、極めてこの重大な課題でダブルスタンダードをとっておられます。
その立場が、全県全ての自治体が、「請願・意見書」ゼロという不名誉な結果に繋がっているのではないでしょうか。
資料1に示したように、佐賀県の山口知事は、賛同の意思を表明しており、文字通り、山口県の異常さは際立っています。改めてこの現状に対しての見解を求めます。
実は、我が山口県は、1995年に、「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める要望決議」を全会一致で採択しています。決議案の紹介議員に名を連ねたのは、共産党の中島修三、浅野謙二、水野純次の3県議でしたが、共産党が紹介議員となった決議案が全会一致で採択されるなど、今では考えられないことでもあります。
決議には、「世界で唯一の被爆国として核兵器の使用・実験・研究・開発・生産。配備・貯蔵などの一切を禁止する核兵器全面禁止。廃絶国際条約を1日も早く締結しよう」、このことを要望しています。まさに今の核兵器禁止条約そのものであります。
県議会の意思として表明したものではありますが、知事もこの決議の意思を尊重すべきではないでしょうか。
この議会決議を踏まえて、核兵器禁止条約の批准に賛同する意思を今こそ表明すべきではありますが、改めて知事に伺います。
●近藤和彦県境生活部長
核兵器禁止条約についての再質問にお答えします。
再質問の中で、1995年に採択をされた「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める要望決議」のご紹介がございましたけれども、先ほど知事が答弁を申し上げている中の繰り返しになりますけれども、この要望決議の主旨も踏まえて、知事の方は核兵器の廃絶自体はこれを強く願っているということを答弁をさせていただいております。
ただ、その手法についてですね、国の専管事項である安全保障とも密接に関わっていることから、国民の命と平和な暮らしを守る観点で、国において、しっかり検討を進めていただきたいというふうに答弁をさせていただいています。
したがいまして、国の取組を尊重する立場に立って、国に対しては、核兵器禁止条約への批准を求めることまでは考えてはおりません。
米軍岩国地基地について
1、県の態度表明について
◎木佐木大助議員
質問の第2は、米軍岩国基地についてです。
県は、7月22日、米軍岩国基地所属の第5空母航空団に配備されている空母艦載機について、①4戦闘攻撃飛行隊のうち1個飛行隊をFA-18スーパーホーネットからF-35Cに、②C-2輸送機の飛行隊からCMV-22オスプレイの飛行隊に、それぞれ更新するという国の説明に対して、32項目の照会を行ない、8月29日、その回答等を踏まえ、知事は「今回の機種更新等は、基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではなく、また、地元市町の見解を踏まえ、私としては、今回の機種更新等について理解をする」と表明されました。
わが党は、断じて容認できません。理由は2つあります。
1つは、県の態度表明が余りに性急だったことです。これまでの新たな配備や機種変更時の対応を振り返ると、資料2の通り、国の通告から態度表明までの期間は、KC130空中給油機の移駐は316日、CH53Dヘリコプターの配備は62日、F35B戦闘機への機種変更は121日です。いずれのケースも県議会の本会議、常任委員会での質疑を経て、対応が決められています。
今回の機種変更は、県内初のオスプレイ配備という大問題が含まれ、不安をもつ県民も少なくありません。にも関わらず、国の通告から態度表明まで45日しかなく、県議会各会派への説明も、議会での質疑も経ないまま容認されました。議会軽視も甚だしい対応であり、強く抗議するものです。なぜ議会への説明を行わなかったのか、なぜ急いだのか、お尋ねします。
●田中康史総務部理事
まず、岩国基地における機種更新等について、議会への説明をなぜ行わなかったのか、なぜ急いだのかとのお尋ねです。
今回の機種更新等については、7月15日の国からの説明以降、国への照会や回答等について、その都度、県議会の各会派や基地議連の関係議員の皆様に御報告しながら、地元市町と合同で検証を行い、「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではない」と整理しました。
この検証結果等を踏まえて、地元市町で検討が行われ、先月28日までに、すべての地元の市町長が機種更新等に理解を示す旨の見解を表明されたことから、県は、地元の意向を尊重するという立場に立って、理解をするという判断に至ったものであり、県として適切に対応したと考えています。
◎木佐木大助議員《再質問》
基地問題であります。基地議連とか各会派に説明しているなどと言っておりますが、正式な本会議や常任委員会では一切議論はしておりません。8月29日の容認は一旦保留し、今議会で総務企画委員会で改めて経緯を説明すべきではありませんか、お尋ねします。
●田中康史総務部理事
米軍岩国基地問題についての再質問にお答えします。
まず、機種更新について、県の態度表明が性急であり、容認を一旦保留し、改めて経緯を説明すべきとのお尋ねです。
先ほども御答弁しましたとおり、今回の機種更新等につきましては、国の説明等を踏まえ、地元市町と合同で検証を行い、「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではない」と整理したところです。
この検証結果等を踏まえて、地元市町で検討が行われ、先月28日までに、すべての地元の市町長が機種更新等に理解を示す旨の見解を表明されたことから、県は、地元の意向を尊重するという立場に立って、理解をするという判断に至ったものであり、県として適切に対応したと考えており、その判断を保留する考えはありません。
県としましては、地元の意向を尊重するという立場に立って理解をするという判断に至ったものでございまして、県としては、適切に対応したというふうに考えております。
◎木佐木大助議員《再々質問》
基地問題、これについては議会軽視であるということは、結果的にお認めになったというふうに判断しますが、これでよろしいか改めて確認します。
●田中康史総務部理事
米軍岩国基地問題についての再々質問にお答えします。まず、今回の機種更新の態度表明について、議会軽視ではないかとのお尋ねだったかと思います。
県としては、地元市町と合同で検証を行って、基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものでないというふうに整理し、そしてまた、地元市町でも検討が行われまして、すべての地元の市町長が機種更新等に理解を示すという旨の見解を表明されましたことから、県は、地元の意向を尊重するという基本姿勢、立場に立って、理解をするという判断に至ったものであり、対応としては適切だったというふうに考えております。
2、オスプレイそのものの危険性について
◎木佐木大助議員
2つは、オスプレイそのものの危険性です。
県の「検証結果」では、オスプレイの安全性について、「米国政府自身が開発段階で安全性・信頼性を確認している」としています。墜落事故を踏まえた現段階で米国政府は「安全性・信頼性」を確認しているのですか。お尋ねします。
そして、「国として、機体の安全性について問題ない」と結論づけていますが、米国政府も「機体の安全性について問題ない」と明言しているのですか。お尋ねします。
オスプレイが配備されている沖縄県の玉城デニー知事は、「構造的な欠陥を放置したまま、運用上の点検だけでオスプレイは問題ないというような形では、私は納得できない」とコメントしています。
構造的な欠陥をもつオスプレイの岩国基地への配備は容認すべきではありません。見解を問います。
●田中康史総務部理事
次に、オスプレイの安全性について、現段階で、米国政府が「安全性・信頼性」を確認しているのか、米国政府も「機体の安全性に問題ない」と明言しているのかとのお尋ねにまとめてお答えします。
このたびの事故を受けて、国が米側に確認したところ、「機体自体の設計を変更するなどの必要性はなく、機体自体の安全性にも問題はなく、また、飛行の安全にかかわる構造上の欠陥がないことにも変わりはない」旨の説明を受けたとのことでした。
次に、オスプレイの配備は容認すべきでないとのお尋ねです。
オスプレイを含む航空機の安全性については、専門的な知見を有する国の責任において確保されるべきものであり、また、国の説明については、一定の理解ができるものと考えられることから、県として、オスプレイヘの機種更新について、理解するという判断に至ったものです。
◎木佐木大助議員《再質問》
オスプレイの危険性についてですが、オスプレイは6月段階では、岩国基地が中継拠点として使われるという問題でしたが、今度はいよいよ常駐配備であります。改めて指摘しますが、米海軍航空システム司令官が、今年6月12日、アメリカ議会下院の公聴会で「航空機の安全に影響する問題に十分に対処できると確信するまでは、無制限の運用復帰を認めることはない」、そして全面的な運用開始は「来年半ば以降になるとの見通し」を示しました。
防衛省は勝手なことを言っていますが、設計・開発・製造したアメリカが、「少なくとも現段階では安全だと太鼓判は押せない」との見解が出されています。それでも山口県は安全だと言い張るのでしょうか、お尋ねします。
●田中康史総務部理事
オスプレイの配備についてでございますが、米議会下院の公聴会での米軍司令官の発言を引かれまして、れでも県は安全だと言うのかというお尋ねでございました。
国の説明によれば、「事故原因に対応した各種の安全対策措置を講じることで安全に運用を行うことが可能であり、米側からは、機体自体の安全性にも問題はなく、また、飛行の安全にかかわる構造上の欠陥がないことにも変わりはない旨の説明を受けている」とのことでした。
県としては、オスプレイを含む航空機の安全性については、専門的な知見を有する国の責任において確保されるべきものであり、また、国の説明については、一定の理解ができるものと考えています。
米軍関係者による犯罪について
質問の第3は、米軍関係者による犯罪についてです。
在沖縄米兵による性的暴行事件が沖縄県に伝えられていなかった問題を契機に、1997年に日米両政府が合意した「在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続」は機能不全に陥っていることが明らかになりました。
資料3の通り、警察庁の「米軍人、軍属及び家族による刑法犯検挙状況」によると、1989年から今年5月まで35年間の刑法犯検挙件数は328件で、うち窃盗犯が212件、粗暴犯が48件、その他54件などです。2014年から今年5月に限ると刑法犯検挙件数は52件です。このうち中四国防衛局から通報があったのは県内で発生した事案に限るとわずか5件に留まっています。県は「通報手続」が適切に運用されているとお考えですか。伺います。
●田中康史総務部理事
米軍関係者による犯罪についての2点のお尋ねにお答えします。
まず、通報手続の運用についてです。
国においては、プライバシーや捜査・公判への影響等に関する捜査当局の判断を前提として、個別具体的な事案の内容に応じ、適切に対応しているとのことであり、県としては、事件・事故発生時の通報は適切に行われているものと考えています。
◎木佐木大助議員《再質問》
通報は適切であったなどとんでもない話でありますが、米軍関係者の犯罪、特に性犯罪の根絶のためには、せめて沖縄県議会が全会一致であげた意見書に沿った対応を国に求めるべきであります。改めて伺います。
県警本部長にも伺いたいのですが、「身柄引き渡し条項」を早急に改定することは、これまで、法と証拠に基づき、身体を張って米兵犯罪と向き合ってきた山口県警察として、必要不可欠な課題と考えますがお尋ねします。
米軍人等による性犯罪については、少し遡りますが、2008年3月24日の参院予算委員会で、我が党の井上議員が提出した「米軍人等による主な性犯罪」と題する資料に、①1996年8月12日、岩国市内で米兵が被害者を強姦、②1998年6月28日、岩国基地内で米兵が被害者を強姦という2件の性犯罪があった事が記されています。
この資料は外務省において把握している事案であります。
この2件について県警本部に伺ったところ、「県警本部としては承知していない」との回答でした。
米軍から外務省に情報提供されたものの、県警や山口県、岩国市には伝えられていなかった。要するに「握りつぶされた」としか考えられません。
私は、絶対にあってはならない対応だと考えますが、県及び県警本部長のお考えをお尋ねします。
オスプレイや米艦船の無通告寄港、いまだにさっぱりわからない燃料タンクの5倍化など、これまでも多くの課題がありました。今回、米軍関係者の刑法犯の通報を巡る問題も新たに発覚しています。
今こそこうした問題を一歩でも解決するために、1991年を最後にこの30年以上も開店休業・さぼり続けてきた「岩国日米協議会」を再開すべきであります。改めて見解を求めます。
●田中康史総務部理事
次に、米軍関係者の犯罪についての御質問でございました。
沖縄県議会の意見書と同様の対応を国に求めるべきですが改めて伺うとの質問だったと思います。
米軍関係者による犯罪はあってはならないものであり、先ほども御答弁しましたが、県では、これまでも、政府要望や基地関係県市町連絡協議会の要望活動、渉外知事会を通じて、米軍関係者の事件・事故の防止に向けた規律の厳正な保持や日米地位協定の改定などを、国や米側に対し、要望しているところです。
県としては、引き続き、あらゆる機会を通じて、国や米側に対し、粘り強く働きかけてまいります。
次に、日米地位協定の関係で、身柄引き渡し条項を早急に改定すべきとのお尋ねであったかと思います。
お示しの日米地位協定の条項の改定については、渉外知事会において、これまでも、日本側が要求する全ての場合における、被疑者の起訴前の引き渡しについて、日米両政府に対し、要望しているところです。
県としては、引き続き、課題をともにする関係都道府県と連携し、国や米側に粘り強く働きかけてまいります。
次に、米軍人による性犯罪について、1996年、1998年の事案を引かれてのお尋ねです。
県では、米軍関係者の事件・事故に関する文書について、保存期間を10年としており、保存期間を経過していることから、お示しの事案について、国からの情報提供の有無を含めて、確認することができません。
次に、様々な問題に関連して、岩国日米協議会を再開すべきとのお尋ねです。
岩国日米協議会そのものは長年開催していないものの、県や地元岩国市は、基地との情報交換や懇談の場など、さまざまな機会を通じて、その時々の重要な課題について、協議や要請を行ってきております。
そのため、協議会の開催がなくとも、対応に支障が生じるものではないと考えておりますが、今後とも、地元岩国市の意向を尊重しながら、適切に対応してまいります。
◎木佐木大助議員《再々質問》
米兵犯罪についてですが、過去にあった米軍岩国基地の米兵による強姦事件について、保存期間は10年であり、確認できないとの答弁でした。しかし、参院予算委員会の提出資料に、外務省が知り得た事件の概要が記され、県警も県当局も知らず、マスコミ報道もできない、外務省が県警並びに県、岩国市に通報しなかった事実は、明らかではないでしょうか。この点について、改めて答弁を求めます。
●田中康史総務部理事
過去にあった米軍関係者の性犯罪に係る事案について、事実が明らかではないかとのお尋ねだったかと思いますが、先ほども御答弁しましたとおり、お示しの事案につきましては、公文書の保存期間の経過により、県として、国からの情報提供の有無を含めて確認することはできないところです。
◎木佐木大助議員
看過できないのは、女性の人権や尊厳をないがしろにする性犯罪である。1989年からでは不同意性交が3件、不同意わいせつは5件発生し、うち4件は2014年以降である。この4件は1件も県に通報されていない。
県によると、米軍関係者による事件について、米軍に抗議と再発防止を申し入れた事案は、この5年間に12件あるが、性犯罪は1件もない。「通報」されていないためである。
米軍は、性犯罪を秘匿したうえ、起訴や処罰を受けたのかも闇の中、再発防止の措置もとられたかわからない。
沖縄県議会は、7月10日、①被害者への謝罪及び完全な補償、②被害者への丁寧な精神的ケアとセカンドレイプの防止の徹底、③米軍構成員等による犯罪事案は、沖縄県等への迅速な通報ができるよう、日米合同委員会を通じた断固たる措置、④日米地位協定の抜本改定を求めた意見書を全会一致で採択した。
県としても同等の要望を国に求めるべきと考えるが、伺う。
●田中康史総務部理事
次に、性犯罪に関して、沖縄県議会と同等の要望を国に求めるべきとのお尋ねです。
県では、これまでも、政府要望や地元2市2町とで構成する基地関係県市町連絡協議会の要望活動を通じて、米軍関係者の事件・事故の防止に向けた規律の厳正な保持や、被害者への適切な対応などについて、国や米側に対し、要望しているところです。
また、本年7月に、沖縄県における米軍関係者による性犯罪の情報伝達が見直されたことを踏まえ、基地を抱える都道府県で構成する渉外知事会において、関係自治体への通報の徹底や、日米地位協定の司法手続き全般の見直しなどを、国に対し、要請したところです。
米軍関係者による犯罪はあってはならないものであり、県としては、引き続き、あらゆる機会を通じて、国や米側に対し、粘り強く働きかけてまいります。
◎木佐木大助議員《再質問》
「身柄引き渡し条項」を早急に改定することは、県警として「必要不可欠な問題」と考えるがいかがか。
また、平成8年及び平成10年に岩国市内で米兵が強姦事件を起こしたとされている。この2件の事件について、県警では把握がないということだが、米軍から外務省に情報提供されたものの、県警や県、岩国市には伝えられず、握りつぶされたとしか考えられないが、県警本部長の考えはいかがか。
●熊坂隆県警本部長
米軍関係者による犯罪についての御質問についてお答えいたします。
まず、身柄引き渡し条項の改定につきましては、県警察は、お答えする立場にありませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
次に、平成8年及び平成10年の2件につきましては、県警察においては、平成8年及び平成10年に、米軍関係者による強姦事件を検挙したとして犯罪統計に計上されているものはないということでございます。
なお、いずれにいたしましても、県警察としては、米軍犯罪も含め各種犯罪を認知した場合には、法と証拠に基づいて、厳正かつ適正に捜査を行ってまいります。
国のエネルギー政策について
1、第7次エネルギー基本計画
◎木佐木大助議員
質問の第4は、国のエネルギー政策についてです。
1つは、第7次エネルギー基本計画についてです。
2021年10月に閣議決定された現行の計画は、原発を「重要なベースロード電源」としつつ「可能な限り原発依存度を低減する」としています。ところが岸田首相は22年、原発を「最大限活用する」という方針へ急転換し、23年には新増設や老朽原発の60年超の運転を可能にすることを盛り込んだ「GX推進戦略」を閣議決定しました。
共産党県議団は先月22,23の両日、政府交渉を行ない、経済産業省に対し、「GX推進戦略」を次期エネルギー基本計画に反映させず、原発ゼロに転換するよう要請しました。しかし、同省は「生成AIの普及やデータセンターの増加などで電力需要が加速度的に増えていく」ことを強調し、「原子力発電は大きなツールになる」とあからさまでした。
「可能な限り原発依存度を低減する」という方針は、福島第一原発事故の痛苦の教訓を踏まえたものです。この方針を投げ捨てて、原発への依存度を高めることは原発の「安全神話」に立ち戻ることにほかならず、到底、容認できないと考えますが、県の見解を伺います。
また、「電力需要の加速度的な増加」が見込まれるのなら、それを野放しにせず、適正な規制を講じるとともに、再生可能エネルギーの促進と省エネの推進に力を注ぐよう国に求めるべきと考えますが、お尋ねします。
●鈴森和則産業労働部理事
国のエネルギー政策についての御質問のうち、第7次エネルギー基本計画に関する2点のお尋ねにまとめてお答えします。
お示しのGX推進戦略は、第6次エネルギー基本計画を踏まえ、取組等を取りまとめるものであること、そして、今回示す方策は全て第6次エネルギー基本計画の方針の範囲内のものであることを明記しており、県としてもそのように受け止めています。
現在、国においては、第6次エネルギー基本計画策定時からのエネルギー情勢の変化などを踏まえ、本年5月からエネルギー基本計画の見直しの議論が行われているところです。
エネルギー政策は国家運営の基本であり、原子力や再生可能エネルギーをどう利用するか、省エネをどのように推進するかは、安全性の確保を大前提に、安定供給、環境適合、経済効率性という基本視点の下、国の責任において示されるべきものです。
したがいまして、県として、お尋ねのような、見解を述べることや、要請を行うことは考えていません。
2、使用済み核燃料「中間貯蔵施設」について
◎木佐木大助議員
2つは、使用済み核燃料「中間貯蔵施設」についてです。
日本原燃は先般、青森県六ケ所村に建設中の使用済み核燃料再処理工場の稼働時期を2年半程度遅れると発表しました。実に27回目の先延ばしです。このため中国電力が関西電力と共同して上関町に計画している使用済み核燃料「中間貯蔵施設」に対して、「永久保存」になりかねないと危惧する世論が高まっていますが、県の認識を伺います。
●鈴森和則産業労働部理事
使用済み核燃料「中間貯蔵施設」についてです。
お示しの再処理工場のしゅん工時期が見直されたことについては、報道等により承知していますが、上関町の使用済燃料中間貯蔵施設については、施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、県としての見解を申し上げる状況にはないものと考えています。
◎木佐木大助議員《再質問》
エネルギー政策の問題ですが、県民の安心・安全を守る立場から、少なくとも「可能な限り原発依存度を低減する」こうした基本方針は、堅く、堅持するよう改めて国に確認するべきであります。改めて伺います。
●鈴森和則産業労働部理事
原発依存度低減に係る方針の国への確認についてです。
エネルギー政策は国家運営の基本であり、原子力をどのように利用するかについては、安全性の確保を大前提に、国の責任において判断されるべきものです。
このため、県としては、お尋ねのような確認を行うことは考えていません。
◎木佐木大助議員《再質問》
使用済み核燃料再処理工場の問題ですが、稼働延期は27回目であります。現時点で竣功時期は全く見通せません。
たとえ再処理工場が稼働にこぎつけても、高レベル放射性廃棄物の処分場は適地調査の目途すら立たない。国が原子力政策の根幹としている核燃料サイクルは破綻していると考えますが、この点も伺います。
●鈴森和則産業労働部理事
次に、核燃料サイクルについてです。
繰り返しになりますが、エネルギー政策は国家運営の基本であることから、核燃料サイクルをどうするかについても、国の責任において判断されるべきものであり、核燃料サイクルは破綻しているかどうかについて、県として見解を述べることは考えていません。
下関北九州道路について
1、小倉東断層の危険性について
◎木佐木大助議員
質問の第5は、下関北九州道路についてです。
1つは、小倉東断層の危険性についてです。
北九州市小倉から関門海峡を跨ぎ、下関市彦島福浦を経由して旧彦島有料の直下・西山・迫から武久町の間に小倉東断層が走っています。地表の長さは約13km、地下の断層面は23km。右横ずれを主体として逆断層成分を含み、マグニチュード7・1の地震の可能性があります。
2018年11月議会で、この危険性を質したのに対して、当時の土木建築部長は、「学識経験者や国土技術政策総合研究所から『事前に必要な対策を行えば、計画に問題ない』との見解を得たところであり、無謀とのご指摘は当たらないものと考えている」と答弁されました。「事前に必要な対策」とは何か。また、その対策は行われたのか、現時点で「危険性はまったくない」と責任が持てるのか、それぞれについて見解を示してください。
●大江真弘土木建築部長
まず、小倉東断層の危険性についてです。
小倉東断層については、国の地震調査研究推進本部における調査において、当該道路の海峡部付近に、断層の存在の可能性があると指摘されていることは承知しています。
これも踏まえ、海峡部の構造形式については、国と2県2市による検討会において、断層変位の影響を受けにくく、柔軟な対応が可能である吊橋形式による橋梁案が妥当とされたところです。
その後、国の計画段階評価において、橋梁構造に精通した学識経験者から「断層位置を避けて吊橋の主塔を設置することが、断層変位に対応するための前提条件であり、そのためには主塔部等でのボーリング調査が必要」という見解が示されています。
今後、事業主体により、ボーリング調査等が実施され、その結果を踏まえ、適切に対応されるものと考えています。
次に、県主催の公聴会での様々な疑問にどう応えていくのかについてです。
2、県主催の公聴会について
◎木佐木大助議員
2つは、県主催の公聴会についてです。
8月20日、都市計画決定手続きの一環として地元・彦島で県主催の公聴会が開催され、3人の住民が意見表明されました。「誰が望み、誰のための事業なのか」、「災害時の代替となるのか」、「貴重な自然が破壊される」など様々な疑問が出されました。この疑問に県はどう応えていくのか、伺います。
●大江真弘土木建築部長
公聴会での意見については、今後行う都市計画案の縦覧に合わせて、意見に対する県の考え方とその対応をお示しすることとしています。
3、下関北九州道路整備促進大会について
◎木佐木大助議員
3つは、下関北九州道路整備促進大会のあり方です。
2014年度以降、コロナで中止した2回をのぞき、11回の促進大会が開催され、各界からの意見提言が行われています。違和感をもったのは、山口県側は昨年の大会では小学6年生、今年の大会では中学校生徒会を提言発表者にしていたことです。
ご承知の通り、下関北九州道路の事業化に対しては賛否両論あります。こうした事業の促進大会の発表者に小中学生を選び、推進の意見を述べさせるのは、政治利用の疑いがもたれます。不適切だとはお考えにはなりませんか。知事並びに教育長にお尋ねします。
●大江真弘土木建築部長
整備促進大会のあり方についてです。大会においては、これまでも、地域の課題や将来像、当該道路への期待など、幅広い立場・世代の方から生の声をいただいており、小中学生から意見発表をいただいたことについて、不適切であるとは考えていません。
●根ケ山耕平副教育長
県内の小中学校では、郷士への誇りと愛着をもち、主体的に社会の形成に参画する態度を育むために、地域の自然や歴史、産業等の地域資源を生かした学習を教育課程に位置付けています。
こうした学習の一環として、児童生徒が、地域の課題や当該道路への期待、地域の将来像などを取りまとめ、整備促進大会で発表したものであり、このことが不適切であるとは考えていません。
◎木佐木大助議員《再質問》
下北道路の問題で、促進大会の問題ですが、6月議会でも指摘しました事業費が天井知らずに膨らみかねない問題や、事業主体が全く決まっていない問題、これらはきちんと説明したのでしょうか。あまりにも酷い政治利用ではないかと思います。
北九州側はせめて大学生だけが出てきます。どのような経緯で、小中学生をつかったのか、またどのような説明・資料を使ったのか、改めて伺いたいと思います。
●大江真弘土木建築部長
まず、事業費の問題や事業主体が決まっていないことを説明したのかとのお尋ねについてです。
小中学生に対しては、地域や道路の現状や課題、下関北九州道路の計画の概要を中心に説明しています。なお、事業費や事業主体については、説明しておりません。
次に、促進大会にどのような経緯で小中学生をつかったのかとのお尋ねについてです。
小学校については、以前、小学校側から地域を知る学習の一環として、下関北九州道路に関する説明の依頼があり、下関北九州道路に関する出前授業を行っていたところです。
こうした経緯も踏まえ、地元の方にも相談した上で、小学校へ発表を依頼したものです。
また、中学校については、地元の方々に相談し、紹介をいただいて、中学校へ発表を依頼したものです。
次に、どのような説明・資料を使ったのかとのお尋ねについてです。
小中学生に対して、写真やイラスト等を用いて、地域の課題や、下関北九州道路の概要、道路が造られることによる周辺への影響等について説明しています。
公立大学の自治について
◎木佐木大助議員
質問の第6は、公立大学の自治についてです。
6月13日、広島高裁において、当時、下関市立大学経済学部長・理事であった飯塚靖先生の「理事解任は無効」とし、同大学法人に未払い報酬55万円を含む計60万円の解決金の支払い義務づける「勝利的和解」が確定しました。
この「和解」は、憲法第23条「学問の自由、大学の自治」にのっとり、「公共の利益のため事実に基づいた大学運営批判を行う自由」をもつことを認めたと同時に、公立大学法人においては「大学の自治への配慮」が求められていることや、営利法人と異なり「組織運営には公益性」が認められるものであって、役員の忠実義務も「公益という観点が不可欠」であることも確認された、「画期的な判決」でもあります。
その上で今、問われているのは、2020年10月23日の下関市立大学第8回理事会において、飯塚理事の「理事解任」を推し進めた当時の山村理事長や川波学長、ハン・チャンワン副学長、砂原事務局長らの責任問題であります。
当該理事会で最も強硬に「飯塚理事解任」を主張したハン氏は現学長であり、また川波氏は特別招聘教授、砂原氏は特命教授として君臨し続けています。今後、下関市立大学が高等教育機関として不可欠な「大学の自治」を取り戻していく上で、この3氏に対する責任問題は避けて通れません。県の見解を伺います。
同時に、「大学の自治」を蹂躙するに至った、現在の「定款の欠陥」問題、「定款変更を強行」した設置権者・下関市と、地独法第122条第3項又は第4項に示された権限・責任をもちながら、何ら手を打たず事態を悪化させてきた認可権者・山口県の責任も極めて重大です。
飯塚理事が解任された2020年10月末、下関市立大学は地独法第17条第4項に基づき、理事の解任を地域社会に対して公表しています。
しかし、広島高裁での「和解」のとおり、この解任は無効であることが確定しました。
下関市立大学は同じ地独法第17条第4項に基づき「飯塚理事の解任が無効」であったことを地域社会に公表しなければなりません。そうでなければ理事失格とされた飯塚先生の尊厳は回復されません。
山口県は地独法第122条第3項又は第4項に基づき、下関市立大学に対して直ちに「理事解任無効」を公表するよう指導する最低限の責任がありますが、答弁を求めます。
●永富直樹総合企画部長
公立大学の自治についての2点のお尋ねにまとめてお答えします。
地方独立行政法人法の規定に照らし、県は、大学の業務運営に関して指導・助言を行う権限は有していません。
このため、お尋ねのありました、当時の理事の責任や、先般の和解結果の公表については、どこまでも大学において自主的・主体的に判断し、対応されるべき事柄であり、県として、指導を行う考えはありません。
◎木佐木大助議員《再質問》
また再び山口県認可権者は権限を持たない、とんでもない発言をされました。改めて伺います。地独法第122条第3項・第4項はどう書いてあるのか改めて伺いたいと思います。
ここに、権限どころか責任が明記されています。この点では、高裁で判決が確定したところであります。山口県は公然と地独法違反を、このまま黙認していくのか改めて伺います。
●永富直樹総合企画部長
まず、地方独立行政法人法の記載内容に関する御質問ですが、第122条第3項と第4項には設立団体である下関市や公立大学法人に対し、必要な措置を講じることを求めることができる旨、規定をされていますけども、同条第6項において、業務運営に関するものは除かれる旨の規定が置かれております。
従いまして、第2間のこのままとするのかとのお尋ねについては、先ほど御答弁しましたとおり、県は大学の業務運営に関して指導・助言を行う権限を有しておりませんので、大学において、自主的。主体的に判断されるものであり、県として指導する考えはありません。
◎木佐木大助議員《再々質問》
地独法122条第3項第4項について、権限はあるが今回の場合は違う、ということでの判断でよろしいでしょうか。
●永富直樹総合企画部長
第122条第3項、第4項に必要な措置を講ずることができる旨、規定されておりますけれども、先ほど御答弁したとおり、第6項で業務運営に関することは除くとの規定がありますので、大学の業務運営に関して指導。助言を行う権限を県は有していないということでお答えをしたものです。
(2024年9月25日)